メバルはその大きな瞳と美しい姿で、多くのアクアリストを魅了する海水魚です。釣りの対象としても人気が高いメバルですが、実は水槽での飼育も可能で、その独特の生態を間近で観察する楽しみがあります。
この記事では、メバル飼育の基本的な知識から、日々の管理における具体的なポイント、さらにはトラブル対策まで、初心者の方でも安心して飼育を始められるように、網羅的に解説していきます。
メバルの飼育について

メバルってどんな魚?
メバルの飼育はできる?難しい?
メバルの寿命はどれくらい?
メバルの成長速度とサイズ
メバルに与える餌の種類と選び方
メバルの値段と入手方法
メバルは懐く?
メバルは混泳できる?
メバルってどんな魚?

メバルは、カサゴ目メバル科に属する魚で、日本の北海道から九州まで、沿岸の広い範囲に生息しています。主に岩礁地帯や海藻が豊かな藻場を好み、大きな目が張り出している特徴的な顔つきが、名前の由来(眼張)となりました。
体色は生息環境に深く関係しており、黒っぽい「クロメバル」、赤みがかった「アカメバル」、白っぽい「シロメバル」など、多様な色彩変異も観賞魚としての大きな魅力の一つです。
この魚は典型的な夜行性で、日中は岩陰や海藻の間に巧みに身を隠して休息し、周囲が暗くなる夕方から夜にかけて活発に動き出し、餌を探して泳ぎ回ります。水槽内でもこの習性は変わらず、夜間に観察することでメバルの本来の生き生きとした姿を見ることができます。
メバルの飼育はできる?難しい?
メバルの飼育は、適切な準備と知識があれば十分に可能です。しかし、金魚やメダカといった淡水魚の飼育経験しかない方にとっては、海水を用意し、その水質を維持する必要があるため、少し難易度が高く感じられるかもしれません。
特に、水温と塩分濃度の管理はメバルの健康に直結するため、日々のチェックが欠かせません。ただ、基本的な管理のポイントさえ理解し、必要な設備をしっかりと揃えれば、メバル自体は比較的丈夫で環境の変化にもある程度は耐えることができる魚です。そのため、初心者であっても、丁寧な管理を心がけることで十分に長期飼育を楽しむことができます。
メバルの寿命はどれくらい?
メバルの寿命は、適切な飼育環境下で平均して5年から10年ほどと、観賞魚としては比較的長寿な部類に入ります。自然界の厳しい環境下ではさらに長生きする個体も報告されており、その生命力の強さがうかがえます。
水槽という限られた空間でその寿命を全うさせてあげるためには、日々の細やかな管理が非常に重要になります。特に、安定した水温と清浄な水質の維持は絶対条件です。アンモニアや亜硝酸といった有害物質が検出されないクリーンな環境と、ストレス要因の少ない静かな飼育場所を提供することが、メバルを病気にさせず、長く元気に飼育するための最も重要な鍵となります。
メバルの成長速度とサイズ
メバルの成長速度は、水温や餌の質・量、飼育密度など様々な要因に影響されますが、一般的に飼育下ではかなりゆっくりと成長していきます。生まれたばかりの稚魚は非常に小さいですが、順調に育てば1年で10cm程度にまで成長します。
成魚になると、平均して20cmから、種類や個体によっては30cm近くまで大きくなることもあります。この最終的なサイズをあらかじめ想定し、飼育を始める段階から60cm以上の十分な大きさの水槽を用意することが、メバル飼育を成功させるための大前提です。小さな水槽では、メバルが窮屈なだけでなく、成長が妨げられたり、ストレスから病気になったりする原因にもなります。
メバルに与える餌の種類と選び方
メバルは完全な肉食性の魚です。自然界では、小さな魚、エビやカニといった甲殻類、ゴカイやイソメなどの多毛類を捕食しています。飼育下で健康を維持させるためには、この食性を十分に考慮した餌を与える必要があります。
基本となる主食は、栄養バランスに優れた海水肉食魚用の人工飼料が良いでしょう。それに加え、食欲を刺激し、より自然に近い栄養を摂取させるために、冷凍のクリル(オキアミ)やブラインシュリンプ、生きたイサザアミや小エビなどを副食として時々与えるのが理想的です。
餌のバリエーションを豊かにすることは、メバルの健康を維持し、飽きさせないための重要な工夫です。ただし、与えすぎは水質悪化の最大の原因となるため、2~3分で食べきれる量を1日に1回、活動的になる夕方から夜にかけて与えるのが良いでしょう。
メバルの値段と入手方法
メバルの値段は、そのサイズ、種類(色)、そして入手経路によって幅があります。一般的に、観賞魚として流通している10cm未満の幼魚であれば、1匹1,000円から3,000円程度で販売されていることが多いです。
これらのメバルは、海水魚を専門に扱うアクアショップや、品揃えの豊富な大型ペットショップで入手することができます。また、釣りで自分で採集した個体を飼育することも魅力的な選択肢ですが、その場合はいくつかの注意点があります。
釣り針によるダメージを最小限に抑え、輸送中の水温や酸素にも気を配る必要があります。さらに、自然界から採集した個体は、病気や寄生虫を持ち込むリスクがあるため、必ず別の水槽でトリートメント(薬浴や経過観察)期間を設けることが不可欠です。
メバルは懐く?
メバルは犬や猫のように人に懐く魚ではありません。しかし、知能が高いため、飼い主を認識することは可能です。毎日の餌やりを続けることで、「この人が来ると餌がもらえる」と学習し、水槽の前に人が立つと近寄ってくるようになります。
メバルは飼育5日目とは思えんほど寄って来るようになった(ある意味閲覧注意かもね) pic.twitter.com/FGSS1FqTMe
— ちゃん氏 (@monnonkm) November 3, 2022
この瞬間は、飼育者にとって大きな喜びとなるでしょう。ただし、手で触ろうとしたり、驚かせたりすると強いストレスを与えるため、観察は静かに行うことが大切です。
メバル飼育
だいぶ水槽に慣れてくれた😭 pic.twitter.com/zv93IcwS6p— まっち (@match_928) June 20, 2025
メバルは混泳できる?
メバルの混泳は可能ですが、混泳させる相手を慎重に選ぶ必要があります。メバルは肉食魚であり、自分の口に入るサイズの魚やエビ、カニは、ためらうことなく捕食してしまいます。
そのため、デバスズメダイやカクレクマノミといった小さく温和な観賞魚との混泳は、絶対に避けるべきです。
もし混泳を考えるのであれば、メバルと同程度のサイズで、同じく底層で生活し、少し気の強い性質を持つカサゴやソイ、アイナメといった根魚の仲間が適しています。これらの魚は、お互いの力関係を認識し、適切な距離感を保ちやすいため、比較的トラブルが起こりにくい組み合わせと言えます。
| 混泳相性 | 具体的な魚種 | 注意点 |
| 相性が良い | カサゴ、ソイ、アイナメなど | 口に入らない同程度のサイズであること。縄張りを主張しすぎないよう、隠れ家を十分に用意することが絶対条件。 |
| 相性が悪い | スズメダイ、ハゼ類、小型のエビなど | サイズに関わらず、メバルにとっては格好の餌となってしまうため、混泳は絶対に避けるべき。 |


メバルの飼育のポイントと注意点

メバルの飼育に必要なもの一覧
メバルに最適な水温と水質とは?
メバルが餌を食べないときの対処法は?
長く元気に飼うために意識したいコツ
メバルの飼育に向いている人とは?
初心者が陥りやすいメバル飼育のミス
メバルの飼育に必要なもの一覧
| 必要なもの | 目的・ポイント |
| 60cm水槽セット | 飼育の基本となる水槽。セット品にはフィルター等が含まれることが多い。 |
| 照明 | 観賞や水槽内の環境を整えるために使用。 |
| フィルター | 水質をきれいに保つための必須機材。 |
| ヒーター | 冬場の水温を一定に保つために必要。 |
| ライブロック | メバルの隠れ家や、水質を安定させるバクテリアの住処になる。 |
| 底砂 | 水槽の底に敷く砂。景観を整える。 |
| 人工海水のもと | 家庭で安全な海水を作るために必須。 |
| 比重計 | 海水の塩分濃度を正確に測るために使用。 |
メバル飼育を始めるにあたり、たくさんの機材があって何から揃えれば良いか迷ってしまいますよね。そんな初心者の方にまずおすすめなのが、「GEX ラピレスRV60GT LEDセット」です。

このセット商品を選べば、メバル飼育に不可欠な水槽本体はもちろん、照明、フィルター、ヒーターが全部ついてくるので、一つ一つ選ぶ手間が省けて非常にお得です。
基本的な機材が一度に揃うこのセットをベースに、あといくつか海水魚飼育ならではのアイテムを追加していきましょう。まずは、メバルの隠れ家となり、水質を安定させてくれるバクテリアの住処にもなる「ライブロック」ですね。
そして、水槽の景観を整える「底砂」も用意しましょう。
最後に、安全な海水を作るための「人工海水のもと」と、その塩分濃度を正確に測るための「比重計」を揃えれば、いよいよメバルを迎える環境は万全です。
海水の作り方はこちらを参考にしてください!
メバルに最適な水温と水質とは?
メバルは日本の沿岸、つまり四季のある温帯の海に生息しているため、熱帯魚のような高い水温は好みません。飼育における最適な水温と水質の管理は、メバルの健康そのものを左右する最も重要な要素です。これらの数値を常に把握し、維持することが飼育者の責任となります。
| 管理項目 | 最適な範囲 | ポイント |
| 水温 | 15℃〜20 | この範囲を外れるとストレスを感じ、病気になりやすくなる。急激な温度変化は絶対に避けるべきで、特に夏場の水温上昇には細心の注意が必要。 |
| 塩分濃度(比重) | 1.020~1.023 | 人工海水のもとを使い、比重計で正確に測定することが重要。足し水は必ず真水で行う。 |
メバルが餌を食べないときの対処法は?
メバルが突然餌を食べなくなった場合、パニックにならず、原因を一つずつ探っていくことが大切です。まず第一に考えられるのは、水槽に導入したばかりで、新しい環境へのストレスや警戒心から食べられないケースです。
この場合は、数日間そっとしておくことで自然に食べ始めることがほとんどです。次に疑うべきは、水質の悪化です。特に目に見えないアンモニアや亜硝酸の濃度が上昇している可能性が高いです。すぐに水質検査を行い、数値に問題があれば速やかに水換えを実施しましょう。
また、いつも同じ人工飼料を与えていることで、単純に飽きてしまっている可能性も考えられます。その際は、活きエビや冷凍クリルなど、嗜好性の高い餌を与えて食欲を刺激してみるのが効果的です。これらのいずれにも当てはまらない場合は、病気の初期症状である可能性を疑い、体表やヒレ、泳ぎ方などを注意深く観察する必要があります。
長く元気に飼うために意識したいコツ
メバルを長く元気に飼育するための最大のコツは、「変化の少ない安定した環境を維持する」ことに尽きます。水温、水質、塩分濃度、そして日々の餌やりの時間など、できるだけ生活のルーティンを変えないように心がけることが、メバルに余計なストレスを与えないための基本です。
また、メバルは物音や振動にも敏感な魚なので、水槽のレイアウトを頻繁に変更したり、水槽の近くで大きな音を立てたりするのを避けることも大切です。そして何より、最も重要な習慣は、毎日数分でも良いのでメバルの様子を愛情を持って観察することです。
普段の行動や体の状態を把握していれば、食欲の低下や体色の変化といった些細な異常にもすぐに気づくことができ、それが病気の早期発見と早期対応、結果として長期飼育へとつながります。
メバルの飼育に向いている人とは?
メバルの飼育は、日々の地道な管理や観察を、作業としてではなく楽しみとして捉えられる人に向いています。カラフルな熱帯魚のように常に泳ぎ回るわけではなく、岩陰からじっとこちらを見ているような、静かな時間が長い魚です。
そのため、水槽の前で静かに魚の自然な仕草を観察するのが好きな、思慮深いタイプの人には最適と言えるでしょう。また、海水水槽の複雑な仕組みや、水質を維持するための化学的な知識について、積極的に学ぶ意欲があることも重要です。生き物のために、手間や時間を惜しまない丁寧な性格の人が、メバルという奥深い魚の飼育を成功させることができるでしょう。
初心者が陥りやすいメバル飼育のミス
海水魚飼育の初心者がメバルで失敗してしまう原因には、いくつかの典型的なパターンがあります。最も多いのは、「水槽の立ち上げ」を急いでしまうことです。新品の水槽に海水を張ってすぐ魚を入れるのではなく、魚が出す排泄物を分解してくれる有益なバクテリア(ろ過バクテリア)が十分に繁殖するまで、待つ必要があります。
この期間を省略すると、水質が急激に悪化し、メバルを死なせてしまいます。また、夏場の高水温対策を怠ることも、日本の気候では致命的なミスに繋がります。メバルにとって30℃近い高水温は耐えられません。初期投資を惜しんで水槽用クーラーの必要性を軽視しないことが、夏を無事に乗り越えるために不可欠です。
メバルの飼育を成功させるための実践ガイド

メバルに最適な水槽レイアウト
隠れ家の作り方とストレス対策
水換えの頻度と管理方法
冬・夏の温度管理のポイント
飼育に関するよくある質問(FAQ)
メバルの飼育 まとめ
メバルに最適な水槽レイアウト
メバルが心から落ち着ける水槽レイアウトを作るには、彼らが本来暮らしている自然の生息地、つまりゴツゴツとした岩礁地帯を水槽内に再現することが理想です。
底には、砂底や、掃除がしやすい大磯砂などを薄く敷きます。そして、レイアウトの主役となるライブロック(生きたバクテリアが付着した岩)や、形の良い岩を複雑に、かつ安定するように組み上げて、メバルが隠れることができる暗いスペースをたくさん作ってあげましょう。
物陰から大きな目でじっとこちらをうかがう姿は、まさに自然のメバルの姿そのものであり、メバル飼育の最大の醍醐味と言えるでしょう。
隠れ家の作り方とストレス対策
隠れ家は、メバルにとって単なる休憩場所ではなく、精神的な安定を保つための「安全地帯」であり、ストレス対策の要です。ライブロックをアーチ状に組んで下の空間をトンネルにしたり、複数の岩を重ねて複雑な洞窟を作ったりすることで、効果的な隠れ家になります。
レイアウトを組む際に重要なのは、メバルが体をすっぽりと隠せる大きさの隙間を、水槽内の複数箇所に、できれば異なる高さに作ることです。これにより、メバルは危険を感じた時や他の魚から逃れたい時に、すぐに避難できる場所を確保でき、安心して生活できます。この安心感が、ストレスを軽減し、病気への抵抗力を高めることにも直接つながります。
水換えの頻度と管理方法
清浄な海水を維持するため、定期的な水換えは飼育者が行うべき最も重要なメンテナンス作業です。水換えの適切な頻度は、水槽のサイズ、収容している魚の数や大きさ、フィルターの能力によって異なりますが、一般的な目安としては、1~2週間に1回、水槽全体の4分の1から3分の1程度の量を交換します。
水換えで重要なのは、ただ水を入れ替えるだけではないということです。交換する際は、あらかじめ用意しておいた新しい人工海水の温度と比重(塩分濃度)を、必ず現在泳いでいる水槽の水と正確に一致させてから、ポンプなどを使ってゆっくりと注ぎ入れるようにしてください。この丁寧な一手間が、メバルに急激な環境変化によるショック(ペーハーショックなど)を与えず、健康を守ることに繋がります。
冬・夏の温度管理のポイント
メバルの飼育で最も注意とコストを要するのが、一年を通した徹底した温度管理です。水温の変化に弱いメバルにとって、日本の四季は大きな試練となります。冬場は、水槽用ヒーターと、設定温度を正確に保つためのサーモスタットを必ず使用し、水温が15℃以下に下がらないように厳密に管理します。
ヒーターは経年劣化や故障の可能性があるため、2年程度で交換するか、万が一に備えて予備を用意しておくと安心です。一方、より深刻なのが夏場の水温上昇です。室内のエアコン管理だけでは、照明やポンプの熱で水温は容易に25℃を超えてしまいます。
特に近年の猛暑を考えると、長期飼育を本気で目指すのであれば、初期投資はかかりますが水槽用クーラーの設置がほぼ必須と言えるでしょう。
飼育に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、メバル飼育に関して特によく寄せられる質問とその答えを、さらに詳しく掘り下げて解説します。飼育者が抱きやすい疑問を解消し、より安定した飼育を目指しましょう。
「メバルの飼育にプロテインスキマーは絶対に必要ですか?」という質問は、機材をそろえる段階で非常に多くの方が悩みます。 答えは、「絶対的な必須機材ではありませんが、設置することで水質管理が格段に楽になり、長期的な安定飼育を目指すなら強く推奨される」となります。 メバルのような肉食魚は、タンパク質を多く含む餌を食べ、糞もするため、水中の有機物(見えない汚れ)が増えやすい傾向にあります。プロテインスキマーは、特殊な泡の力でこれらの有機物が有害なアンモニアなどに分解される前に、物理的に水槽外へ除去してくれる優れた装置です。 スキマーがない場合は、より頻繁な水換え(例えば週に1回ではなく、3~4日に1回など)で汚れに対応する必要がありますが、スキマーを設置することで水換えの頻度を抑え、水質を常に高いレベルで維持しやすくなります。特に初心者の方ほど、管理を助けてくれるスキマーの恩恵は大きいと言えるでしょう。
次に、「釣りで釣ったメバルは飼えますか?」という質問も非常に多いです。 答えは、「可能ですが、ショップで購入する個体よりも飼育難易度は格段に上がります」となります。 その理由は複数あります。まず、釣り針による口やエラへのダメージ、釣り上げられる際の急な水圧の変化、そして輸送中のストレスなど、採集されたメバルは大きな負担を負っています。 もし挑戦する場合は、ダメージを最小限にするため、針は返し(バーブ)のないものを使い、釣り上げたらすぐに針を外して、エアレーションを効かせたクーラーボックスへ移すなどの配慮が不可欠です。 持ち帰った後は、すぐに本水槽へ入れるのではなく、必ず別の「トリートメントタンク(検疫水槽)」で2週間~1ヶ月ほど様子を見ることが重要です。この期間で、持ち込んだ病気がないかを確認し、人工飼料に餌付く練習をさせる必要があります。最初は生きたエビなどから始め、少しずつ冷凍餌、人工飼料へと慣らしていく根気強いトレーニングが成功の鍵となります。
「メバルがずっと隠れて出てきません。病気でしょうか?」という心配の声もよく聞かれます。 これは、メバルの習性を理解することで解決できる場合がほとんどです。メバルは本来、日中は岩陰に潜む夜行性の魚であり、臆病な性格をしています。水槽内でも、明るい時間帯に隠れているのは非常に正常な行動です。 むしろ、水槽内に安心できる隠れ家が十分にないと、メバルは常に落ち着かず、かえってストレスを溜めてしまいます。立派な隠れ家があってそこに隠れているのであれば、それは環境に満足している証拠と捉えることができます。餌の時間になると元気に姿を現し、餌を食べ終わるとまた隠れ家に戻っていくようであれば、健康状態に問題はありません。
最後に、「水槽の水が蒸発したら、海水を足せば良いのですか?」という質問です。 これは海水魚飼育における非常に重要なポイントで、答えは「いいえ、足すのは必ず真水(カルキを抜いた水道水)にしてください」です。 水槽から水分が蒸発する際、水(H₂O)だけが気体になり、塩分は水槽内に残ります。ここに海水を足してしまうと、水槽内の塩分濃度がどんどん濃くなり、メバルにとって危険な状態になってしまいます。蒸発して減った分を補う「足し水」は、必ず塩分の入っていない真水で行う、と覚えておきましょう。この管理を楽にするため、自動で真水を給水してくれる装置も市販されています。
メバルの飼育 まとめ

メバルの飼育は、見た目の美しさと落ち着いた性格、そして夜行性ならではの観察の楽しさが魅力です。海水魚としてのメバルは、正しい設備と知識があれば、初心者でも十分に飼育が可能です。
特に重要なのは、適切な水温と水質の管理、そして隠れ家を確保したレイアウトです。メバルはストレスに敏感な魚なので、安心して過ごせる環境づくりが長生きの鍵となります。また、餌やりの時間を決めてあげることで、少しずつ人に慣れてくれることもあります。
混泳を考える場合は、サイズや性格が近い魚を選び、攻撃性のトラブルを防ぎましょう。日々の観察とケアを大切にすることで、メバルとの穏やかで豊かな時間を楽しむことができます。
美しい姿と静かな魅力を持つメバル。この記事をきっかけに、ぜひ本格的な飼育にチャレンジしてみてください。きっと、水槽の中に新たな発見と癒しが広がるはずです。
関連記事はこちらから!!
カワハギの飼育完全ガイド:初心者でも安心!快適に育てるための飼い方













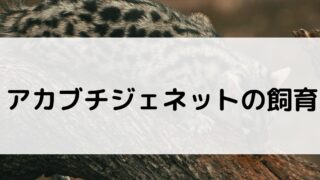



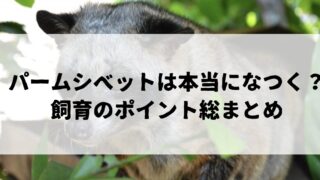




コメント