愛らしくユニークな姿で多くの人々を魅了するウーパールーパー。そのウーパールーパーが突然餌を食べなくなると、飼い主としては非常に心配になることでしょう。「病気なのだろうか?」「飼育環境に何か問題があるのだろうか?」と、様々な不安が頭をよぎるかもしれません。
ウーパールーパーが餌を食べなくなる理由は一つではありません。水温や水質といった環境の問題、ストレス、餌そのものの問題、そして時には病気のサインである可能性も考えられます。しかし、慌てる必要はありません。一つひとつの原因を丁寧に見極め、適切に対処することで、多くの場合、食欲を取り戻してくれます。
この記事では、ウーパールーパーの食欲不振について考えられる原因を体系的に掘り下げ、ご家庭で今すぐ実践できる具体的な解決策を専門家の視点から詳しく解説します。大切なウーパールーパーの元気を取り戻すために、ぜひ最後までお読みください。
ウーパールーパーが餌を食べない主な原因

ウーパールーパーは非常に繊細な生き物であり、飼育環境の変化やストレスに敏感に反応します。食欲不振が見られた場合、まず初めに疑うべきは病気ではなく、日々の生活環境です。ここでは、環境やストレスに起因する食欲不振の8つの主な原因について解説します。
水温の問題:高すぎる・低すぎる
ウーパールーパーの健康を維持する上で、水温管理は最も重要な要素の一つです。ウーパールーパーの原産地はメキシコの冷涼な湖であり、暑さに非常に弱い生き物です。適正水温は10℃から20℃とされています。この範囲を外れると、ウーパールーパーの体に大きな負担がかかり、食欲不振に直結します。
水温が高すぎる場合、具体的には25℃を超えると深刻な事態に陥ります。高温状態では代謝が異常に活発になり、体力を著しく消耗します。人間で言えば、常に全力疾走しているような状態です。これにより極度のストレスを感じ、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなります。当然、食欲もなくなります。夏場は特に注意が必要で、室温の上昇と共に水温も上昇するため、対策を怠ると命に関わります。対策としては、観賞魚用のクーラーを設置するのが最も確実です。初期投資はかかりますが、最も安全に夏を越すことができます。他には、水槽用のファンを設置して気化熱で水温を下げたり、部屋ごとエアコンで管理したりする方法があります。
逆に、水温が低すぎる場合、特に10℃を下回るような環境では、ウーパールーパーの代謝活動が極端に低下します。冬眠に近い状態となり、活動が鈍り、消化能力も落ちるため、餌を欲しがらなくなります。日本の冬では室内でも水温が10℃を下回ることがあるため、観賞魚用のヒーターを使用して、水温が下がりすぎないように管理することが推奨されます。
まずは水槽に必ず水温計を設置し、毎日現在の水温を把握することから始めましょう。
水質の悪化
見た目が透明な水でも、水質が悪化していることはよくあります。ウーパールーパーは多くの排泄物を出すため、水は目に見えない有害物質で汚染されやすいのです。特に問題となるのが、アンモニアと亜硝酸塩です。これらはウーパールーパーの排泄物や食べ残しの餌が分解される過程で発生し、非常に高い毒性を持っています。
水槽内にこれらの有害物質が蓄積すると、ウーパールーパーはアンモニア中毒や亜硝酸塩中毒を起こします。症状としては、体の動きが鈍くなる、エラが溶けて小さくなる、皮膚が赤く充血する、そして食欲が完全になくなる、といったものが見られます。この状態を放置すると、衰弱して死に至ることも少なくありません。
対策として最も重要なのは、定期的な水換えです。1週間に1回から2回、全体の3分の1程度の水を交換することが基本です。また、ろ過フィルターを適切に設置し、有害物質を分解してくれるバクテリア(硝化菌)を繁殖させることも重要です。水質は見た目では判断できないため、市販の試験薬を使って定期的にアンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩の濃度を測定する習慣をつけることを強く推奨します。
強すぎる水流のストレス
前述の通り、ウーパールーパーは流れのほとんどない湖に生息していた生き物です。そのため、水槽内に強い水流があると、常に泳ぎ続けなければならず、大きなストレスを感じます。ろ過フィルターの排水口から出る水流が直接ウーパールーパーの体に当たっているような状況は、ウーパールーパーにとって快適とは言えません。
絶えず水流に逆らって体勢を維持することは体力を消耗させ、落ち着いて休むことができなくさせます。このようなストレスフルな環境では、食欲が湧かなくなってしまいます。
対策としては、フィルターの排水口の向きを水槽のガラス面に向ける、排水口にスポンジを取り付けて水流を和らげる、シャワーパイプを設置して水流を分散させるなどの工夫が有効です。ウーパールーパーが水槽の隅でじっとしていることが多い場合、水流から逃げようとしているサインかもしれません。
明るすぎる照明
ウーパールーパーにはまぶたがなく、光を直接浴び続けることを嫌います。観賞のために明るい照明を設置している場合、それがウーパールーパーにとっては大きなストレス源になっている可能性があります。強い光にさらされ続けると、ウーパールーパーは物陰に隠れようとし、活動的でなくなります。
ストレス下では食欲も減退します。特に、餌を与える時間帯に煌々と照明がついていると、安心して餌を食べに出てこないことがあります。
対策としては、まず照明の光量を落とすことが考えられます。調光機能のあるLED照明を選ぶと良いでしょう。また、浮草(マツモやアマゾンフロッグピットなど)を浮かべることで、自然な日陰を作り出すことができます。照明は観賞する時間帯だけ点灯し、普段は部屋の明かり程度にするなど、点灯時間を管理することも重要です。
隠れ家の不足
明るすぎる照明の問題とも関連しますが、水槽内に安心して隠れられる場所がないと、ウーパールーパーは常に周囲を警戒し、落ち着くことができません。外敵から身を守る場所がないという本能的な不安が、ストレスとなって食欲不振を引き起こします。
特に、新しい環境に来たばかりのウーパールーパーや、サイズの小さい個体にとっては、隠れ家の存在が精神的な安定に大きく寄与します。
対策は非常に簡単で、水槽内に隠れ家を設置してあげるだけです。素焼きの土管や植木鉢を割ったもの、爬虫類用のシェルター、あるいはアクアリウム用に販売されている流木や岩のオブジェなどが適しています。ウーパールーパーが体をすっぽりと隠せるサイズのものを、一つか二つ入れてあげましょう。
同居している生体との相性
ウーパールーパーは基本的に単独飼育が推奨される生き物です。他の種類の魚と一緒に飼育すると、様々なトラブルが発生し、それがストレスとなって餌を食べなくなることがあります。
例えば、動きの素早い魚はウーパールーパーの餌を横取りしてしまったり、ウーパールーパーの特徴的な外鰓(フサフサのエラ)をつついて怪我をさせてしまったりすることがあります。逆に、ウーパールーパーが口に入るサイズの魚やエビを食べてしまうこともあります。
ウーパールーパー同士の複数飼育でも注意が必要です。特に体の大きさに差があると、大きい個体が小さい個体を攻撃したり、共食いしてしまったりする危険性があります。常に他の個体を警戒しているような状況では、安心して餌を食べることができません。もし複数飼育をしていて食欲不振の個体がいる場合は、一時的に別の水槽に隔離して様子を見ることをお勧めします。
急な環境の変化
購入して自宅に連れてきたばかり、水槽のレイアウトを大幅に変更した、普段より多くの水を一度に交換した、といった急激な環境の変化も、ウーパールーパーにとって大きなストレスとなります。
新しい環境に適応するには時間が必要です。その間、警戒心から食欲が落ちることがよくあります。これは「水に慣れていない」状態で、一種のショック症状とも言えます。特に水合わせを慎重に行わずに新しい水槽に移した場合、水温や水質の急変に体がついていけず、体調を崩してしまいます。
対策としては、何事も「ゆっくり、少しずつ」を心掛けることです。水槽に迎える際は、時間をかけて水合わせを行う。水換えは定期的に、決まった量を行う。レイアウトの変更も、一度に全てを変えるのではなく、少しずつ行うのが望ましいです.
騒音や振動
ウーパールーパーは耳で音を聞く能力は高くありませんが、側線器官を通じて水中の振動には非常に敏感です。そのため、水槽がテレビやスピーカーの近く、人の往来が激しいドアのそば、あるいは工事現場の近くなど、騒音や振動が多い場所に置かれていると、継続的なストレスを感じることになります。
人間にとっては気にならないレベルの振動でも、ウーパールーパーにとっては大きな脅威に感じられることがあります。この慢性的なストレスが、食欲の低下につながることは十分に考えられます。
対策は、水槽を家の静かで安定した場所に設置することです。人の出入りが少なく、大きな音や振動が発生しない場所を選んであげましょう。
ウーパールーパーが餌を食べない時の対策:餌と与え方の見直し

飼育環境に問題が見当たらない場合、次に考えられるのは「餌」そのものや「与え方」に原因がある可能性です。ウーパールーパーにも食の好みがあり、与え方一つで食べるかどうかが変わることもあります。ここでは、餌に関する8つの改善策を見ていきましょう。
餌の好みが合わない
人間にも好き嫌いがあるように、ウーパールーパーにも餌の好みがあります。今まで食べていた餌を急に食べなくなることもありますし、新しい餌に全く興味を示さないこともあります。ウーパールーパーの主食には、主に人工飼料(固形フード)、冷凍アカムシ、活き餌(イトミミズやドジョウなど)があります。
もし特定の人工飼料だけを与えていて食べなくなったのであれば、別のメーカーの人工飼料を試してみる価値はあります。また、人工飼料に興味を示さない個体でも、生き物の匂いや動きに強く反応することがあります。冷凍アカムシや活き餌を与えてみることで、食欲が刺激されるケースは非常に多いです。
餌のサイズが不適切
餌の大きさがウーパールーパーの口に合っていないと、食べたくても食べられない、あるいは食べるのをためらってしまうことがあります。特に体の小さい幼体に対して、大きすぎる人工飼料を与えると、飲み込めずに吐き出してしまいます。これを繰り返すうちに、その餌自体を食べようとしなくなります。
逆に、成長した大きな個体に対して、小さすぎる餌(例えば冷凍アカムシだけ)を与えていると、満足感が得られず、食べる意欲がわかないこともあります。
ウーパールーパーの口の幅の半分以下の大きさの餌が、一つの目安となります。成長に合わせて、餌の種類やサイズを適切に見直してあげることが大切です。
餌の鮮度・劣化
見落としがちですが、餌の鮮度は非常に重要です。特に人工飼料は、開封してから時間が経つと湿気を吸って酸化し、風味や栄養価が落ちてしまいます。人間が古い食べ物を食べたくないのと同じで、ウーパールーパーも劣化した餌は食べようとしません。
冷凍アカムシも、一度解凍したものを再冷凍すると品質が著しく落ちます。与える分だけをその都度解凍するようにしましょう。
対策として、人工飼料は開封後、密閉容器に入れて冷暗所で保管し、1〜2ヶ月を目安に使い切るようにしましょう。大袋で買う方が経済的ですが、使い切る前に劣化してしまうリスクも考慮する必要があります。常に新鮮な餌を与えることを心掛けてください。
給餌方法の見直し
どのように餌を与えているかも、ウーパールーパーの食欲に影響します。例えば、餌を水槽にばらまくだけの「置き餌」方式では、ウーパールーパーが餌に気づかない、あるいは底に落ちた餌を食べるのが下手な個体もいます。
食欲が落ちている時は、長いピンセットで餌を掴み、ウーパールーパーの目の前で優しく揺らして見せると効果的です。餌の存在をアピールし、動きで興味を引くことができます。これにより、どの個体がどれだけ食べたかを正確に把握できるというメリットもあります。ただし、ピンセットで体を傷つけないように注意が必要です。
給餌頻度と空腹
「餌を食べない」と心配している飼い主の中には、実は餌を与えすぎているケースもあります。ウーパールーパー、特に成長した大人の個体は、毎日餌を必要とするわけではありません。消化能力にも限界があり、満腹の状態が続けば、当然次の餌には興味を示しません。
幼体(15cm未満)の頃は毎日、あるいは1日2回与えるのが良いですが、亜成体から成体(15cm以上)に成長したら、2〜3日に1回程度の給餌で十分です。単純にお腹が空いていないだけかもしれませんので、一度、給餌の間隔をあけて様子を見てみましょう。
給餌時間の変更
ウーパールーパーは薄明薄暮性、あるいは夜行性の傾向が強い生き物です。そのため、昼間の明るい時間帯よりも、部屋の照明が落ちた夕方から夜にかけての時間帯の方が、活動的になり、食欲も増すことがあります。
もし日中に餌を与えていて食いつきが悪い場合は、給餌の時間を夜に変えてみてください。生活リズムに合ったタイミングで与えることで、あっさりと食べ始める可能性があります。飼い主の生活スタイルに合わせて、ウーパールーパーが最もリラックスしている時間帯を探ってみましょう。
ウーパールーパーが餌を食べない時に疑うべきこと

環境と餌の両方を見直しても食欲が戻らない場合、残念ながら病気や体調不良の可能性を考えなければなりません。ここでは、食欲不振を引き起こす可能性のある病気や異常、そしてそれらを未然に防ぐための予防法について解説します。
外見の異常チェック
まずは、ウーパールーパーの体をよく観察し、異常がないかを確認しましょう。
- 白い綿のようなもの: 体表に白い綿のようなものが付着している場合、水カビ病(真菌性疾患)の可能性が高いです。免疫力の低下が原因で発症し、食欲不振を伴います。
- 皮膚の充血や出血: 皮膚の一部が赤くなっていたり、出血したりしている場合、細菌感染症(レッドレッグなど)や、どこかに体を擦り付けた外傷が考えられます。痛みから食欲がなくなることがあります。
- エラの状態: 外鰓(フサフサのエラ)が溶けていたり、小さくなっていたりするのは、水質悪化によるストレスの典型的なサインです。
- 体の浮き: 体が常に浮いてしまい、底に沈めない状態は、ガスが溜まっている、あるいは浮き袋の異常などが考えられます。
これらの異常が見られた場合は、病気の治療が必要です。
便秘・お腹の張り
餌の消化がうまくいかず、便秘になってしまうことがあります。お腹にガスや未消化物が溜まると、腹部が不自然に膨らみ、苦しくて食欲がなくなります。餌の与えすぎや、消化の悪い餌を与え続けた場合に起こりやすいです。
軽度の便秘であれば、数日間絶食させることで自然に排泄されることがあります。また、最終手段として「冷蔵庫治療」という方法もありますが、これはウーパールーパーに大きな負担をかけるため、正しい知識を持った上で、自己責任で行う必要があります。基本的には、まずは絶食と水質改善で様子を見るのが安全です。
床材の誤飲
これは事故に近いですが、非常に危険な状態です。ウーパールーパーは餌を吸い込むようにして食べるため、床に敷いている砂利などを餌と一緒に誤って飲み込んでしまうことがあります。飲み込んだ砂利が消化管に詰まってしまうと、腸閉塞(イレウス)を引き起こします。
こうなると餌を食べられなくなるのはもちろん、排泄もできなくなり、最悪の場合は死に至ります。お腹が硬く膨らんでいる、食欲がない、といった症状が続く場合は、誤飲を疑う必要があります。
これを防ぐためには、床材の選択が極めて重要です。誤飲の心配がないベアタンク(何も敷かない)にするか、口に入らないほど大きな石を置く、あるいは粒が非常に細かく万が一飲み込んでも排泄されやすい極細目のサンドを使用するのが安全です。一般的な観賞魚用の砂利は、ウーパールーパーの飼育には絶対に使用しないでください。
病院へ行く判断基準
家庭での対処には限界があります。以下のような重篤な症状が見られる場合は、迷わずエキゾチックアニマルを診療できる動物病院に連れて行ってください。手遅れになる前に、専門家の診断を仰ぐことが命を救う鍵となります。
予防法①:定期的な水換え
これまで述べてきた多くの問題は、水質の維持によって防ぐことができます。全ての基本は、定期的な水換えです。これにより、有害なアンモニアや亜硝酸塩の濃度を低く保ち、ウーパールーパーのストレスを軽減し、免疫力を正常に維持することができます。面倒に感じるかもしれませんが、これが最も効果的で重要な健康管理です。
予防法②:栄養バランスの取れた餌
特定の餌だけを与え続けるのではなく、複数の種類の餌をローテーションで与えることで、栄養の偏りを防ぐことができます。例えば、主食は栄養バランスの取れた人工飼料とし、おやつとしてたまに冷凍アカムシや活き餌を与える、といった形です。バランスの取れた食事は、病気に負けない強い体を作ります。
予防法③:日々の健康観察
毎日、ほんの少しの時間で良いので、ウーパールーパーの様子を観察する習慣をつけましょう。「元気に泳いでいるか」「体のどこかに異常はないか」「エラのフサフサは元気か」「お腹はスリムか」などをチェックします。この日々の観察こそが、病気や異常の早期発見につながり、深刻な事態になる前に対処することを可能にします。
ウーパールーパーが餌を食べない まとめ

ウーパールーパーが餌を食べない時、その背後には様々な原因が隠されています。しかし、その多くは飼育環境の見直しや、餌やり方法の工夫によって解決できるものです。まずは慌てずに、この記事で紹介した「環境・ストレス」「餌・与え方」「病気・予防」の3つのステップに沿って、原因を一つずつチェックしてみてください。
飼い主の日々の丁寧な観察とケアが、ウーパールーパーの健康を守る一番の秘訣です。この記事が、あなたの大切なウーパールーパーの食欲不振を解決し、再び元気な姿を取り戻すための一助となれば幸いです。
関連記事はこちらから!!








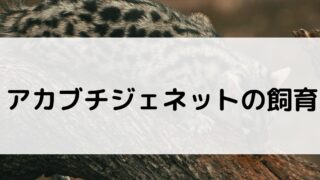














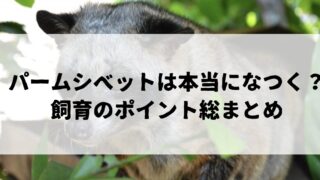



コメント