「文鳥って小さくて可愛いし、飼いやすそう!」
「鳴き声もきれいで癒されるって聞いたけど、本当に初心者でも大丈夫?」
そんなイメージを持って文鳥の飼育を検討している方も多いのではないでしょうか。
ですが、実際に飼ってみると「思ったより手がかかる」「意外に鳴き声が響く」「旅行に行きづらい」など、飼育前には想像できなかったデメリットに直面することも少なくありません。

この記事では、「文鳥を飼うデメリット」というテーマにフォーカスして、飼う前に知っておきたい注意点や、後悔しないための対策、よくある誤解などをわかりやすく解説します。
文鳥は決して「飼いにくいペット」ではありませんが、正しい知識を持たずに迎えると、飼い主も文鳥も不幸になってしまうことも…。
大切な命を預かるからこそ、後悔のない選択をするための情報を、この記事でしっかり確認しておきましょう!
✔ 文鳥を飼うデメリットは「鳴き声」「お金」「手間」などがある
✔ 繊細で甘えん坊な性格のため、放置するとストレスになる
✔ 正しく対策すれば、デメリットは最小限に抑えられる
✔ 飼い始める前に、自分のライフスタイルとの相性を見極めることが大切
- 文鳥を飼うデメリット まずは文鳥の基本情報
- 文鳥を飼う前に知っておくべき14のデメリット
- 1. 朝が早い
- 2. 鳴き声が意外と大きい
- 3. 放鳥が必要|毎日30分以上遊ばせる手間と時間
- 4. 糞が多い|ケージや放鳥中の掃除が大変な現実
- 5. ひとりぼっちが苦手で寂しがり屋|留守番が多いとストレスに
- 6. 脱走リスクが高い|ほんの少しの隙間でも逃げてしまう
- 7. 家具や電化製品へのイタズラ
- 8. 病気の兆候がわかりにくい|気づいた時には重症化も
- 9. 鳥専門の病院が少ない|通院の困難さ
- 10. アレルギーの原因になることも
- 11. 羽の生え変わり時期は部屋が散らかる|掃除の労力増大
- 12. ケージの掃除頻度が高い|清潔維持の重要性
- 13. 旅行や外出時に預け先が見つかりにくい|自由な行動の制限
- 14. 思っている以上にお金がかかる|初期費用とランニングコスト
- 文鳥を飼うデメリットを乗り越えるために:準備と心構え
文鳥を飼うデメリット まずは文鳥の基本情報

文鳥ってどんな鳥?
文鳥は、スズメ目カエデチョウ科に属する、インドネシアのジャワ島やバリ島が原産の美しい鳥です。愛玩鳥として世界中で親しまれており、その特徴は、黒い頭、白い頬、灰色の体にピンク色のくちばしと足を持つことです。
品種改良によって、白文鳥、桜文鳥、シナモン文鳥など、様々な美しい色合いの文鳥が存在します。体長は約13〜15cmと小さく、手のひらに乗るくらいの愛らしい大きさです。さえずりは個性的で、特にオスは美しい声で鳴き、メスは「チュンチュン」と鳴くことが多いです。非常に賢く、人によく慣れることで知られており、飼い主と深い絆を築くことができます。
文鳥の寿命
文鳥の平均寿命は、およそ7年から10年ほどと言われています。適切な飼育環境とバランスの取れた栄養管理、そしてストレスの少ない穏やかな生活を送らせてあげることで、10年以上長生きする文鳥も珍しくありません。
文鳥はなつく?
はい、文鳥は非常によく人に懐きます。特に雛の頃から飼育し、飼い主がこまめにスキンシップをとることで、まるで家族の一員のように懐いてくれます。飼い主の指に乗ったり、肩に止まったり、手の中で安心して眠ったりする姿は、文鳥を飼う大きな喜びの一つです。個体差はありますが、名前を呼ぶと反応したり、飼い主の動きをじっと見つめたりと、感情豊かに接してくれることもあります。
文鳥の餌
文鳥の餌は、主にシード(主食)と副食に分けられます。主食としては、麻の実、粟、稗、黍などがバランス良く配合された文鳥専用の混合シードが一般的です。最近では、必要な栄養素がすべて含まれているペレットも利用されていますが、文鳥によっては好みが分かれることもあります。副食としては、ビタミンやミネラルを補給するために、小松菜などの新鮮な青菜を毎日少量与えることが推奨されます(ほうれん草は避けましょう)。
そして、常に新鮮な水を用意し、毎日交換することも忘れてはいけません。換羽期や繁殖期には、普段よりも栄養が必要になるため、獣医師と相談の上、ネクトンなどの栄養補助食品を少量与えることもあります。
文鳥を飼う前に知っておくべき14のデメリット

2. 鳴き声が意外と大きい
3. 放鳥が必要
4. 糞が多い
5. ひとりぼっちが苦手で寂しがり屋
6. 脱走リスクが高い
7. 家具や電化製品へのイタズラ
8. 病気の兆候がわかりにくい
9. 鳥専門の病院が少ない
10. アレルギーの原因になることも
11. 羽の生え変わり時期は部屋が散らかる
12. ケージの掃除頻度が高い
13. 旅行や外出時に預け先が見つかりにくい
14. 思っている以上にお金がかかる
文鳥との生活を後悔しないためにも、まずは具体的なデメリットを徹底的に把握し、飼い主としての覚悟があるかを確認しましょう。
1. 朝が早い
文鳥は、野生の鳥と同じく太陽とともに目覚める習性があります。そのため、日の出とともに活動を開始し、元気いっぱいにさえずり始めます。特に、日照時間が長い春から夏にかけては、毎日午前6時前には「ピッピッ」「チュンチュン」という高らかな鳴き声で目覚めを促されることが珍しくありません。カーテンを閉めていても、文鳥の体内時計は正確です。
都会で暮らす人々にとって、朝の貴重な睡眠時間は何物にも代えがたいものです。ゆっくりと寝ていたい休日の朝も、文鳥のさえずりは容赦なく響き渡ります。朝型の生活に慣れていない人や、睡眠時間を十分に確保したい人にとっては、この早朝のさえずりが慢性的な睡眠不足やストレスの原因となる可能性があります。家族がいる場合は、他の家族の睡眠を妨げてしまう可能性も考慮に入れる必要があります。
2. 鳴き声が意外と大きい
「小鳥だから静かだろう」というイメージは、文鳥に関しては必ずしも当てはまりません。文鳥の鳴き声は、体が小さい割に甲高く、非常に響き渡ります。
特に、オスの文鳥は、求愛行動や縄張りの主張のために頻繁にさえずり、その声量は想像以上に大きくなることがあります。楽しそうにさえずる声は飼い主にとって癒しとなる一方で、近隣住民にとっては騒音に感じられる可能性もゼロではありません。
マンションやアパートなどの集合住宅で飼う場合は、隣室や上下階への配慮が不可欠です。窓を閉めていても、壁や床を通して鳴き声が伝わることもあります。特に、日中に在宅時間が長く、文鳥の活動時間が長い家庭では、近隣トラブルに発展しないよう、事前に防音対策を真剣に検討する必要があります。
3. 放鳥が必要|毎日30分以上遊ばせる手間と時間
文鳥の心身の健康とストレス解消のためには、ケージから出して部屋の中を自由に飛び回らせる「放鳥」の時間が不可欠です。毎日最低でも30分以上は放鳥してあげるのが理想的とされています。文鳥は好奇心旺盛で、部屋の中を探索したり、飼い主の肩に乗ったり、手の上で遊んだりすることで精神的な満足を得ます。放鳥不足はストレスとなり、毛引き症などの問題行動や体調不良につながることもあります。
仕事や家事で忙しい人にとって、毎日決まった時間に放鳥の時間を確保することは大きな負担となる可能性があります。また、放鳥中は文鳥から目を離すことができないため、その時間は他の作業ができません。予測できない急な用事が入った場合など、毎日きっちり時間を確保するのが難しい日もあるでしょう。
4. 糞が多い|ケージや放鳥中の掃除が大変な現実
文鳥は、小さな体の割に排泄の回数が非常に多い動物です。消化が早く、食べたものがすぐに排泄されるため、数分おきにフンをすることも珍しくありません。ケージの中はもちろんのこと、放鳥中は部屋の中を自由に飛び回るため、家具やカーペット、カーテン、家電製品などがフンで汚れることは日常茶飯事です。
常に清潔な状態を保つためには、こまめな掃除が必須となります。ケージ内の糞受けシートの交換や、止まり木の拭き掃除は毎日行い、放鳥中もフンをされたらすぐに拭き取る必要があります。特に、フンは乾燥すると固まって取りにくくなるため、放置することはできません。掃除に時間を割きたくない人や、潔癖症の人にとっては、大きなストレスとなるでしょう。
5. ひとりぼっちが苦手で寂しがり屋|留守番が多いとストレスに

文鳥は非常に社会性が高く、飼い主とのコミュニケーションを強く求める生き物です。まるで人間の子供のように、飼い主への依存度が高く、ひとりぼっちの時間が続くと強いストレスを感じます。このストレスが原因で、食欲不振、毛引き症(自分の羽をむしってしまう行為)、体調不良などにつながることも少なくありません。
長時間家を空けることが多い人や、あまり構ってあげられない環境では、文鳥が精神的に不安定になってしまう可能性が高いです。テレワークなどで家にいる時間が長い人や、文鳥と密なコミュニケーションを取りたいと考える人には向いていますが、日中留守がちな家庭では、文鳥が寂しさから病気になるリスクがあることを理解しておく必要があります。
文鳥を飼う明確なデメリットがひとつ、一生手から離れてくれないから何も作業ができない pic.twitter.com/xZ5p6jnemL
— ハッシー99 (@hassy_white) April 20, 2023
6. 脱走リスクが高い|ほんの少しの隙間でも逃げてしまう
文鳥は体が非常に小さく、俊敏なため、ほんの数センチの細い隙間からでも簡単にすり抜けてしまいます。そのため、脱走のリスクが非常に高い動物であることを常に認識しておく必要があります。
窓の開けっ放しはもちろん、玄関やベランダのドアの開閉時、あるいは宅配便の受け取りなどで人が出入りする際のちょっとした油断が、瞬時の脱走につながることがあります。
一度脱走すると、文鳥は小さくてすばしっこく、そして野生で生きていく術を知らないため、見つけるのは非常に困難です。屋外の環境は文鳥にとって過酷であり、他の鳥や猫などの捕食動物に襲われたり、寒さや暑さ、飢えで命を落とす可能性が非常に高いです。
飼い主は常に窓やドアの施錠を確認し、換気をする際も網戸がしっかり閉まっているか、破れていないかなどを徹底的に確認するなど、目を離さないように細心の注意を払い、二重三重の脱走防止対策が求められます。
拡散希望です
友達の大切な文鳥のへいちゃんがお昼ごろに脱走してしまいました😭
自宅周辺を探していますが見つかりません…
目撃情報などがあればご協力お願いします🙇🙇#文鳥探しています #脱走 #文鳥 #へいちゃん #拡散希望 pic.twitter.com/8NCt2KJBvP— ichigo (@puchi_bebe) June 10, 2025
7. 家具や電化製品へのイタズラ

好奇心旺盛で遊び好きな文鳥は、放鳥中に様々なものに興味を示し、そのくちばしでかじったり、突っついたりする習性があります。特に、電化製品のコード類は、細くてかじりやすいため格好のターゲットとなりがちです。かじられたコードがショートして火災の原因になったり、大切な家電製品が故障したりするリスクがあります。これは単なるイタズラでは済まされない、深刻な危険をはらんでいます。
また、観葉植物の葉をちぎったり、本や雑誌、新聞紙などをボロボロにしたり、木製の家具や壁紙、カーテンなどをかじったりすることもあります。中には、文鳥にとって毒性のある植物もあるため、口にしてしまうと非常に危険です。放鳥中は目を離さず、危険なものや大切なものは文鳥が届かない場所にしまう、あるいは丈夫なカバーで保護するなど、徹底した安全対策とイタズラ対策が求められます。文鳥のために、ある程度の家具の損傷は許容する心構えも必要かもしれません。
8. 病気の兆候がわかりにくい|気づいた時には重症化も
文鳥は、野生の習性として、天敵から身を守るために体調不良を隠そうとする傾向があります。そのため、飼い主が「あれ?少し元気がないかな?」と異変に気づいた時には、すでに病気がかなり進行している、というケースが少なくありません。小さなサインを見逃してしまうと、あっという間に重症化し、手遅れになることも珍しくありません。
文鳥の病気のサインは、食欲不振、フンの形状や色の変化、羽のツヤがなくなる、羽を膨らませてじっとしている、姿勢がおかしい、鳴き声の変化、活動量の低下など、非常に些細なことが多いです。飼い主は、日々の食欲やフンの状態、羽の様子、行動などを細かく観察する習慣を身につけ、わずかな変化も見逃さないようにすることが非常に重要です。少しでもおかしいと感じたら、自己判断せず、すぐに動物病院を受診する判断力も求められます。
9. 鳥専門の病院が少ない|通院の困難さ
犬や猫に比べて、鳥類を専門的に診ることができる動物病院は、残念ながら非常に少ないのが現状です。一般的な動物病院では鳥の診察に対応していないことも多く、いざ文鳥が病気になった時に、自宅から通える範囲に鳥を診られる病院が見つからないという事態も起こり得ます。これは、文鳥の命に直結する深刻な問題です。
遠方の病院まで連れて行かなければならない場合、文鳥への精神的・身体的負担はもちろんのこと、飼い主の交通費や時間的な負担も大きくなります。また、緊急時でもすぐに診察を受けられない可能性があります。飼い始める前に、必ず近隣の鳥専門病院、または鳥の診察が可能な動物病院を複数調べておき、診療時間や休診日、予約の要不要、緊急時の対応なども確認しておくことが非常に重要です。
10. アレルギーの原因になることも
文鳥の羽毛やフンには、アレルギーの原因となる粉塵が含まれていることがあります。特に、子どもやアレルギー体質の人、気管支が弱い人、あるいは過去に動物アレルギーの経験がある人は、文鳥を飼うことでアレルギー症状が悪化したり、新たに発症したりする可能性がゼロではありません。くしゃみ、鼻水、目の痒み、皮膚炎、さらには喘息などの呼吸器系の症状が出る場合があります。
飼い始める前に、家族全員に鳥アレルギーの有無を確認し、もし過去にアレルギー症状が出た経験がある場合は、慎重に検討する必要があります。定期的な掃除や高性能な空気清浄機の使用、加湿器による湿度管理などで軽減できることもありますが、症状が重い場合は、残念ながら飼育を断念せざるを得ない可能性もあります。飼い主自身の健康を守ることもまた、重要な責任です。
11. 羽の生え変わり時期は部屋が散らかる|掃除の労力増大
文鳥には、年に数回「換羽期(かんうき)」という、古い羽が抜け落ちて新しい羽に生え変わる時期があります。この期間は、想像以上に大量の古い羽が抜け落ち、部屋中に舞い散ります。
ケージの周りだけでなく、部屋の隅々、家具の上、棚の中、衣類、さらには食事の中まで、細かな羽が付着することもあります。
こまめに掃除機をかけたり、粘着ローラーを使ったりしても、完全に綺麗にするのは至難の業と感じるかもしれません。特に、アレルギー体質の人にとっては、この時期の羽の舞い散りは大きな問題となり得ます。換羽期は掃除の労力が大幅に増える季節であることを覚悟しておきましょう。また、文鳥自身も換羽中は体力を消耗しやすいため、健康状態に特に注意を払う必要があります。
12. ケージの掃除頻度が高い|清潔維持の重要性
文鳥の健康を維持し、病気を予防するためには、ケージを常に清潔に保つことが非常に重要です。前述の通りフンの量が多いため、毎日の水・エサの交換と、糞受けシート(または敷材)の交換は必須です。さらに、週に数回はケージ全体を分解して洗浄し、止まり木や水入れ、エサ入れなども細菌の繁殖を防ぐために丁寧に洗い、乾燥させる必要があります。
これを怠ると、不衛生な環境が文鳥にとって大きなストレスとなり、細菌感染症や寄生虫などの病気のリスクが格段に高まります。ケージの掃除は、想像以上に頻繁で手間がかかる作業であり、飼い主の責任として毎日欠かさず行う必要があります。清潔を保つためには、飼い主自身の根気と衛生観念が問われます。
13. 旅行や外出時に預け先が見つかりにくい|自由な行動の制限
犬や猫のように、ペットホテルや知人に気軽に預けることが一般的な動物と異なり、文鳥の預け先は非常に限られています。鳥を専門に預かってくれるペットホテルは数少なく、また、鳥の飼育経験がある友人や家族もなかなか見つからないことが多いのが現状です。文鳥は繊細な動物であり、環境の変化に弱い個体もいるため、慣れない場所でのストレスが体調不良につながるリスクもあります。
そのため、長期の旅行や急な出張、飼い主自身の入院などの際に、文鳥の預け先が見つからず、困ってしまうという事態が起こり得ます。信頼できる預け先を確保できないと、飼い主自身の行動が大きく制限されることになります。事前にしっかりとした預け先を探しておくか、誰かに協力をお願いできる環境を整えておくことが、文鳥を飼う上で非常に重要になります。
14. 思っている以上にお金がかかる|初期費用とランニングコスト
文鳥の生体価格は数千円からと比較的安価なため、気軽に飼い始められると思われがちです。しかし、飼育には初期費用だけでなく、継続的な費用がかかることを理解しておく必要があります。
- 初期費用: 文鳥本体の費用に加え、ケージ、エサ入れ、水入れ、止まり木、ブランコなどのおもちゃ、冬場のヒーター、夏場の冷却グッズ、鳥かごカバー、爪切り、体重計、水浴び容器など、基本的な飼育グッズを一式揃えるのに数万円は確実にかかります。**少しでも良いもの、安全なものを揃えようとすると、さらに費用はかさみます。
- ランニングコスト: 毎日の餌代(年間で数千円~1万円程度)、ケージの敷材(新聞紙やペットシート)、定期的なおもちゃの買い替え、そして特に冬場のヒーターによる**電気代は、予想以上に高額になることがあります。さらに、栄養補助のためのサプリメント代なども考慮に入れる必要があります。
- 医療費: 文鳥は体が小さいため、一度病気になると進行が早く、治療費も高額になることがあります。病気になった場合の診察料、薬代、検査費用などは、一回で数千円~数万円かかることもあります。鳥専門の病院は診察料が高めに設定されている場合もあるため、予期せぬ医療費に備えて、ある程度の貯蓄も必要です。
思っていた以上にお金がかかることに驚き、経済的な負担を感じるかもしれません。文鳥を飼うことは、単なるペットではなく、家族の一員として責任を持つことなのです。
文鳥を飼うデメリットを乗り越えるために:準備と心構え

・鳴き声が気になる人は防音ケージを活用しよう
・スキンシップと放鳥時間はバランスが重要
・抜け毛やフンの掃除は朝晩2回がベスト
・近隣の鳥類専門の動物病院を事前に探しておく
・夏冬の室温はペット用サーモスタットで自動管理
・急な外出に備えてペットホテルや預け先を確保
・文鳥を飼って後悔する人の特徴:こんな人は要注意
・文鳥を飼うんじゃなかった 口コミ:飼い主たちのリアルな声
・文鳥を飼うのに向いている人:愛情と責任を持てるあなたへ
・文鳥を飼うデメリット まとめ
文鳥を飼う上でのデメリットは多いですが、適切な準備と心構え、そして具体的な対策を講じることで、多くの問題を解決し、文鳥との豊かな暮らしを実現できます。
文鳥に対しての誤解をなくし、現実を理解する
文鳥を飼い始める前に、まずあなたが抱いているかもしれない「小鳥だから手がかからない」「鳴き声も小さいしマンションでも安心」といった漠然とした誤解や理想像を一度捨て去り、文鳥の生態や習性、そして現実的な飼育環境について深く理解することが重要です。
文鳥は、その小さな体の中に非常に豊かな感情と強い生命力、そして独自の習性を秘めた、愛すべき生き物です。彼らがどのような動物であるかを正確に把握し、その習性に合わせた環境を整えることで、多くのトラブルを未然に防ぎ、文鳥も飼い主もストレスなく共生できるようになります。
インターネットや書籍で情報を集めるだけでなく、実際に文鳥を飼っている人の話を聞いたり、ペットショップの店員に相談したりして、リアルな情報を得ることも非常に役立ちます。
鳴き声が気になる人は防音ケージを活用しよう
文鳥の鳴き声が近隣に響くのが心配な場合は、防音ケージの導入を真剣に検討しましょう。完全に無音になるわけではありませんが、鳴き声を大幅に軽減する効果が期待できます。
市販の防音ケージは高価なものもありますが、DIYで簡易的な防音対策を施すことも可能です。また、ケージを置く場所を工夫したり、厚手の防音カーテンや吸音材を設置したりするのも効果的です。
日中、家にいる時間が少ない場合は、ケージに遮光性のカバーをかけて文鳥の体内時計を調整し、早朝のさえずりを抑える工夫も有効です。
スキンシップと放鳥時間はバランスが重要

文鳥の心身の健康を維持し、ストレスを解消するためには、適度なスキンシップと放鳥時間が不可欠です。しかし、過度なスキンシップや、飼い主への依存度が高すぎる状態は、飼い主が不在になった際に文鳥が「分離不安」を起こし、ストレスや問題行動(毛引きなど)につながる可能性もあります。文鳥にとって安心できる環境と、飼い主との適切な距離感を保つことが大切です。
毎日決まった時間に30分~1時間程度の放鳥を行い、それ以外の時間はケージ内で落ち着いて過ごせる環境を整えるなど、生活にメリハリをつけることが重要です。放鳥中は、文鳥が安全に遊べるよう、部屋の危険物(電化製品のコード類、観葉植物、開いた窓やドアなど)を排除し、目を離さないようにしましょう。
文鳥用の止まり木スタンドやおもちゃを用意して、安全な遊び場を確保するのも良い方法です。また、放鳥中はただ見守るだけでなく、優しく声をかけたり、お気に入りのおもちゃで一緒に遊んだり、手のひらに乗せて優しくなでたりすることで、文鳥との絆を深めることができます。この時間は、文鳥にとっても飼い主にとっても、かけがえのない大切なコミュニケーションの時間となるでしょう。
抜け毛やフンの掃除は朝晩2回がベスト
抜け毛やフンで部屋が汚れるのを防ぎ、文鳥の健康的な環境を保つためには、こまめな掃除が不可欠です。文鳥は消化が早く、フンの量も多いため、これを怠ると不衛生になり、病気の原因にもなりかねません。そのため、朝晩の2回、ケージ周りや放鳥スペースを軽く掃除する習慣をつけましょう。
具体的には、ケージの糞受けシート(新聞紙やペットシーツなど)は毎日交換し、止まり木や水入れ、エサ入れも毎日洗浄することが望ましいです。特にフンは乾くと固まって取りにくくなるため、見つけたらすぐに拭き取ることが大切です。
コードレス掃除機やハンディクリーナー、粘着ローラーなどを活用すると、手軽に効率よく掃除ができます。また、高性能な空気清浄機を設置することで、舞い散る羽毛やフンに含まれる細かな粉塵を減らし、アレルギー対策にもつながります。
床にはビニールシートや汚れてもよいマットを敷くことで、掃除の手間を軽減することも可能です。定期的なケージ全体の丸洗い(週に1回程度)も忘れずに行い、常に清潔な環境を保つことで、文鳥が快適に過ごせるだけでなく、飼い主の負担も軽減されます。
近隣の鳥類専門の動物病院を事前に探しておく

文鳥は体が小さいため、一度病気になると進行が早く、緊急性が高い場合も少なくありません。しかし、犬や猫に比べて、鳥類を専門的に診ることができる動物病院は非常に少ないのが現状です。一般的な動物病院では鳥の診察に対応していないことも多く、いざ文鳥が病気になった時に、自宅から通える範囲に鳥を診られる病院が見つからないという事態も起こり得ます。
万が一の事態に備えて、自宅から通える範囲にある鳥類専門、または鳥の診察が可能な動物病院を複数、事前に調べてリストアップしておきましょう。インターネットでの検索はもちろん、地域の鳥の飼育経験者やペットショップの店員に情報を聞いてみるのも非常に有効です。
診療時間や休診日、予約の要不要、緊急時の対応(夜間診療の有無など)、そしておおよその診察費用なども確認しておくと安心です。可能であれば、文鳥を迎え入れた後、一度健康診断を兼ねて受診してみることを強くお勧めします。
これにより、かかりつけ医との関係を築けるだけでなく、文鳥の現在の健康状態を把握し、いざという時に慌てずに済み、文鳥の命を救う可能性が格段に高まります。
夏冬の室温はペット用サーモスタットで自動管理
文鳥は温度変化に非常に敏感な動物であり、特に寒さに弱いです。冬場はケージ内を適温(一般的に20℃~25℃)に保つためのヒーターが必須となります。しかし、日中や夜間の温度変化に合わせて手動で温度を管理し続けるのは非常に難しいものです。
そこで、ペット用サーモスタットを導入することで、設定した温度で自動的にヒーターがON/OFFされるため、常に室温を一定に保つことができ、飼い主の管理の手間も省けます。これは文鳥の健康を守る上で非常に重要な投資です。
夏場の暑さ対策も同様に重要です。熱中症は文鳥にとって命に関わる危険があるため、エアコンを適切に利用し、部屋全体を冷やすことが重要です(文鳥に直接冷風が当たらないように注意してください)。扇風機も空気の循環には役立ちますが、文鳥に直接風を当てるのは避けてください。また、夏場は水浴びの機会を増やすことも有効です。適切な温度管理は、文鳥のストレスを軽減し、健康寿命を延ばすために不可欠な要素であることを忘れないでください。
急な外出に備えてペットホテルや預け先を確保
飼い主が旅行や急な外出、あるいは自身の体調不良などで文鳥の世話が難しくなる場合に備えて、鳥を専門に預かってくれるペットホテルを探しておくか、信頼できる友人や家族に協力を依頼し、預け先を確保しておくことが非常に重要です。
犬や猫のように、気軽に預けられる施設や人が多いわけではありません。鳥専門のホテルは数が少ないため、長期の旅行などを計画する際は、早めに予約しておく必要があります。
また、普段から他の人や異なる環境に少しずつ慣れさせておくことで、預ける際の文鳥のストレス軽減にもつながります。
万が一の事態に備えて、文鳥の普段の生活リズム、食事内容、好きなこと、苦手なこと、かかりつけの動物病院の連絡先、与えている薬など、詳細な情報をまとめたメモを準備しておくことも忘れずに。これらの準備をしておくことで、飼い主が不在の間も文鳥が安心して過ごせるようになり、飼い主自身の行動も大きく制限されることなく、心のゆとりが生まれるでしょう。
文鳥を飼って後悔する人の特徴:こんな人は要注意
文鳥を飼い始めてから「こんなはずじゃなかった」と後悔しやすい人には、いくつかの共通する特徴が見られます。もしこれらに当てはまる場合は、文鳥を飼うことについてより慎重に検討するか、自身のライフスタイルや価値観を見直す必要があるかもしれません。
- 手間をかけたくない人: 毎日のケージ掃除、水・餌の交換、定期的な放鳥時間の確保、日々の体調チェックなど、文鳥の世話には想像以上に時間と手間がかかります。これらを「面倒」と感じてしまう人には、文鳥の飼育は大きな負担となり、結果的に文鳥にも寂しい思いをさせてしまう可能性があります。
- 完璧主義な人、潔癖症な人: 部屋の汚れ(細かな抜け毛や飛び散るフン)、早朝の鳴き声、好奇心旺盛な文鳥による家具や電化製品へのイタズラなどを一切許容できないタイプだと、常にストレスを感じ、文鳥との共生が困難になるでしょう。ある程度の「おおらかさ」が求められます。
- 時間に余裕がない人: 仕事やプライベートで忙しく、文鳥との放鳥時間やスキンシップの時間を十分に取れない人は、寂しがり屋の文鳥を精神的に不安定にさせてしまう可能性があります。文鳥との触れ合いは、彼らの心身の健康に不可欠です。
- 神経質な人: 早朝の鳴き声、毎日舞い散る細かな抜け毛、そして常に掃除が必要なフンなどに非常に神経質になってしまうと、精神的に疲弊し、文鳥との生活を心から楽しめなくなってしまうかもしれません。
- 衝動的に飼い始める人: 事前の情報収集が不足しており、文鳥の生態や飼育に関する現実的な知識がないまま、見た目の可愛らしさだけで迎え入れてしまうケースです。理想と現実のギャップに直面し、対処しきれなくなることが多いです。
文鳥を飼うんじゃなかった 口コミ:飼い主たちのリアルな声
実際に文鳥を飼い始めた人の中には、以下のような後悔や苦労の声も聞かれます。これらは、あなたが文鳥を迎え入れる前に知っておくべき、飼い主たちのリアルな声であり、貴重な教訓となるでしょう。
【文鳥は可愛い】
☆デメリット
・病院探しが大変
・旅行に行けない(日帰り程度)
・どこでも💩する
・ケージ掃除大変
☆メリット
・可愛い(デメリット帳消し) pic.twitter.com/TYXkxj5YVs— なちこりた*@幻想のカリスマ (@NaTiP_GAME) June 11, 2023
その他にも
- 「まさかこんなに朝早く起こされるとは…。休日の朝もゆっくり寝ていたいのに、文鳥の声で起こされるので寝坊ができないのが本当に辛いです。毎日のことなので、精神的に参ってしまいます。」
- 「部屋中、羽とフンだらけで掃除が追いつきません。文鳥はどこにでも飛んでいくから、気がつくと家具の上や家電製品の裏まで汚れているんです。潔癖症の私にはちょっと耐えられなくて、ストレスが溜まります…。」
- 「旅行に行きたくても鳥を預かってくれるホテルがほとんどなく、気軽に外出できないのが不便すぎます。長期の旅行はもう諦めるしかありませんでした。友達に頼むにも、鳥の世話は難しいと言われてしまって。」
- 「好奇心旺盛すぎて、目を離した隙に電化製品のコードをかじられてPCが壊れてしまいました。まさかこんなにいたずらするとは想像もしていませんでしたし、危険なので常に見ていないといけないのが本当に大変です。」
- 「病気のサインが本当に分かりにくいんです。少し元気がないなと思った時には、もう手遅れで亡くしてしまいました。もっと早く病院に連れて行けばよかったと今でも後悔しています。小さな変化を見逃さない観察力が必要ですね。」
- 「生体価格は安かったのに、意外とお金がかかります。毎日の餌代はもちろん、冬場のヒーターの電気代、いざという時の病院代、新しいおもちゃなど、出費が続くので、もう少し貯金してから飼うべきでした。」
- 「手乗りの文鳥に憧れて飼い始めたのに、なかなか手に乗ってくれない。根気が必要だとわかっていても、思ったより触れ合えないと寂しく感じる時があります。もっと時間をかけてあげればよかったのかな…。」
- 「換羽期は部屋が羽だらけになります。掃除してもすぐにまた抜け落ちるので、本当に終わりがないと感じますね。アレルギー体質なので、この時期は特に辛いです。」
文鳥を飼うのに向いている人:愛情と責任を持てるあなたへ
一方で、文鳥との生活を心から楽しみ、彼らとの絆を深め、幸せな毎日を送っている飼い主さんもたくさんいます。文鳥は、愛情を注げば注ぐほど、飼い主に応えてくれる賢く愛らしい生き物です。彼らの仕草や鳴き声一つ一つが、日々の生活に癒しと喜びを与えてくれます。文鳥を飼うのに向いているのは、以下のような特徴を持つ人です。
- 毎日こまめな世話ができる人: 毎日のケージ掃除、水・餌の交換、糞の処理、定期的な放鳥、日々の体調チェックなど、文鳥のために手間をかけることを苦にせず、むしろ彼らの世話を通して喜びや充実感を感じられる人。ルーティンワークをこなすのが得意な人は特に向いています。
- 早起きが得意な人、または文鳥の鳴き声を楽しめる人: 早朝のさえずりを「目覚まし時計代わり」とポジティブに捉えたり、彼らの元気な鳴き声を心地よく感じたり、生活のリズムとして自然に受け入れられる人。
- 文鳥のいたずらや抜け毛、フンを許容できる人: 少々の汚れや破損は「これも文鳥らしさ」「仕方のないこと」と大らかな気持ちで受け止められる、寛容な心を持つ人。完璧な清潔さを求めすぎないことが、ストレスをためない秘訣です。
- 自宅にいる時間が長く、文鳥と触れ合う時間を十分に確保できる人: 寂しがり屋の文鳥に寄り添い、たっぷりと愛情と時間を注いであげられる環境にある人。在宅勤務者や、家にいる時間を大切にしたい人には特におすすめです。
- 文鳥の小さな変化にも気づける観察力がある人: 日々の食欲や行動パターン、フンの状態、羽のツヤ、姿勢など、細部にわたる健康管理に注意を払い、わずかな異変にもすぐに気づいてあげられる人。早期発見・早期治療が文鳥の命を救います。
- 経済的な負担も考慮できる人: 生体価格だけでなく、継続的な餌代や敷材費、光熱費(特に冬場のヒーター代)、そして予期せぬ医療費など、お金がかかることを理解し、いざという時のための貯蓄もできる経済的な余裕がある人。
- 生涯にわたる責任を持てる人: 文鳥は平均で7~10年、中には15年ほど長生きすることもあります。その一生を愛情と責任を持って見守り、健康な時も、老いて介護が必要になった時も、最期まで寄り添う覚悟がある人。ペットは「物」ではなく、大切な「家族」であると認識できる人こそが、文鳥を飼うのにふさわしいと言えるでしょう。
文鳥を飼うデメリット まとめ

文鳥を飼うことは、確かに多くのデメリットや大変な面、そして飼い主としての深い責任を伴います。しかし、それらのデメリットを深く理解し、適切な対策を講じ、そして何よりも愛情と忍耐、そして責任を持って接することで、文鳥はあなたの日常生活にかけがえのない喜びと癒し、そして温もりをもたらしてくれる、最高のパートナーとなってくれます。彼らの小さな体から放たれる生命の輝き、愛らしい仕草、そして心を込めたさえずりは、あなたの心を豊かにし、日々に彩りを与えてくれるでしょう。
もし、この記事で紹介したデメリットをすべて読み、それでもなお「文鳥を飼いたい!」「この小さな命を家族として迎え入れたい!」という強い気持ちが揺らがなかったのなら、あなたは文鳥を飼うのに向いている人かもしれません。彼らの短い一生を、最大限の愛情と責任を持って支えてあげられるでしょう。文鳥との素敵な生活を送るために、この記事があなたの決断の一助となり、後悔のない選択をするための一歩となれば幸いです。
関連記事はこちらから!!
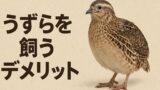

















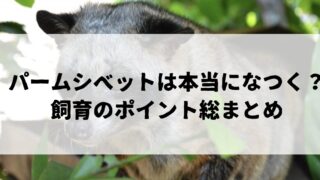






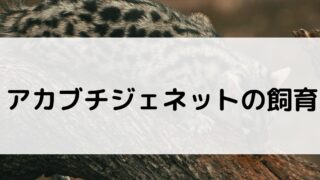






コメント