「イエアメガエルって穏やかで飼いやすいって聞くけど、本当?」 「ペットショップで見たけど、夜の鳴き声とかうるさくないの?」 「カエルって触れるの?毒とか衛生面が心配…」
そんな疑問を持っている方に向けて、本記事ではイエアメガエルを飼育する上での現実的な「デメリット」について詳しく解説します!
正しい知識を身につけ、お迎えした後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためのポイントを押さえましょう!
記事のポイント
✔ 餌は手間と費用がかかる
✔ オスの鳴き声は夜間に響く可能性あり
✔ 掃除を怠ると臭いや衛生面の問題が発生
✔ 皮膚に弱い毒があり、触れ合いには注意が必要
✔ 年間を通した温度・湿度管理が欠かせない
イエアメガエルの飼育 (デメリットを知る前に)

イエアメガエルってどんなカエル?
イエアメガエルは、オーストラリアやニューギニアに住む、ツリーフロッグ(樹上性のカエル)の仲間です。「イエアメ」という名前は、人家の近く(家の雨どいなど)でよく見かけられたことに由来しています。
大きさは、大人のカエルで約7cmから12cmほど。メスの方がオスよりも少し大きくなる傾向があります。体色は美しい緑色が多いですが、環境や気分によって茶色っぽく変化することもありますよ。目の上にある「まぶた」のような皮膚のひだも、特徴的なチャームポイントです。
巨大イエアメガエルを飼い始めて1年経ったらこうなった https://t.co/eV3SjowBIn pic.twitter.com/0IMJ5ZloKF
— ぴよ@カエルと暮らす (@PIYO_KAERU) January 30, 2024
生息地
イエアメガエルのふるさとは、オーストラリアの北部や東部、そしてニューギニア島です。
熱帯雨林や湿度の高い森林地帯が主な住処ですが、人の生活圏にも適応していて、公園の木々や家の窓、雨どい、お手洗いなど、意外と身近な場所にも姿を見せることがあります。
販売場所
イエアメガエルをお迎えしたい場合、爬虫類や両生類を専門に扱っているペットショップ(専門店)で出会えることが多いです。また、全国各地で開かれる爬虫類・両生類の展示即売イベントでも、たくさんのブリーダーさんやショップが出店しているので、お気に入りの一匹を見つけやすいでしょう。
寿命
イエアメガエルは、カエルの中では驚くほど長生きな種類として知られています。適切な飼育環境で健康に育てられた場合、飼育下での平均寿命は、なんと10年から15年ほどと言われています。
大切に飼育された個体の中には、20年以上生きたという記録もあるくらいです。一般的なペットのカエルと比べても、非常に長い付き合いになります。お迎えするということは、それだけ長い時間を一緒に過ごす、大切な家族を迎えることだとぜひ考えてあげてください。
餌
イエアメガエルは肉食性で、主に昆虫を食べます。飼育下では、コオロギやミルワーム、デュビアなどの生きた昆虫を与えるのが一般的ですが、最近では人工餌も選択肢の一つとして注目されています。
人工餌は栄養バランスが整っており、虫を扱うのが苦手な人でも手軽に与えられるのが魅力です。慣れるまでに少し時間がかかる個体もいますが、ピンセットで根気よく与え続けることで食べるようになることも多いです。
イエアメガエルはなつくのか?
「なつく」のイメージが、犬や猫のように飼い主を認識して甘えてくる様子だとすると、イエアメガエルは少し違います。カエルは基本的に、そのような「なつき方」はしません。
しかし、飼育を続けていると、飼い主の顔を覚えてくれるようになります。「ごはんをくれる人」として認識し、ケージの前に立つと「餌かな?」と寄ってきたり、ピンセットから怖がらずに餌を食べたりするようになります。こうした反応は、飼い主さんにとって、とても愛おしく感じられる瞬間ですよ。
イエアメガエル飼育のデメリットとは?

愛らしいイエアメガエルですが、一緒に暮らす上では、知っておかなければならない現実的な側面、いわゆる「デメリット」もあります。お迎えした後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
餌代と手間がかかる
イエアメガエルは、基本的に生きている昆虫を食べます。
動くものに反応して捕食する習性があるため、コオロギやミルワームなどの生き餌を与えるのが一般的です。そのため、常に生きた昆虫をストックしておく必要があり、餌代や管理の手間がかかります。
一方で、最近は人工餌(人工フード)を使う飼育者も増えています。人工餌は栄養バランスが良く、虫を扱うのが苦手な人でも手軽に与えられるのがメリットです。
ただし、イエアメガエルは動く餌しか興味を示さないことが多いため、ピンセットで餌をゆらしたり動かしたりして与える工夫が必要になります。最初は食べない個体もいますが、根気よく続けることで人工餌に慣れてくれる場合もあります。
鳴き声がうるさい場合がある
オスのイエアメガエルは、繁殖期になると「ゲッゲッゲッ…」と意外なほど大きな声で鳴くことがあります。こ
れは縄張りを主張したり、メスを呼んだりする行動です。特に夜間に鳴くことが多く、その音量は個体差もありますが、アパートやマンションなどの集合住宅では、鳴き声が壁を伝わって近隣への騒音にならないか、少し心配になるかもしれません。
メスはあまり鳴かないと言われますが、幼体でのオスメスの判別は難しいため、オスをお迎えする可能性も考えておく必要があります。
ケロケロケロケロ ケロ
#イエアメガエル #カエル #frog pic.twitter.com/M1TpKBDrDG— 𓆏͙まみんと𓆏͙ (@mint_Aoinko) October 4, 2025
臭いがきつい場合がある
イエアメガエル自体が強く臭うことはほとんどありませんが、飼育環境が不衛生になると、特有の臭いが発生することがあります。主な原因は、フンや食べ残した餌の放置です。
高温多湿なケージ内では、これらはすぐに腐敗・雑菌が繁殖し、ツンとしたアンモニア臭や生臭さの原因となります。また、水入れの水を毎日交換しないと、すぐにヌメリや臭いが出始めます。こまめな掃除を怠ると、部屋に不快な臭いが充満してしまう可能性があります。
脱走しやすい
イエアメガエルは、体がとても柔らかく、壁に張り付く力も強いため、飼い主さんが驚くようなわずかな隙間からでも抜け出してしまうことがあります。「こんな所からは無理だろう」という油断が脱走につながります。
ケージの蓋を少し開けたままにしていたり、配線用の小さな穴があったりすると、そこから上手に体をねじ込んで脱走してしまう危険性があります。一度家の中で行方不明になると、家具の裏やエアコンの上など、思わぬ場所に入り込み、見つけるのが非常に困難になるため、厳重な注意が必要です。
皮膚から毒を分泌する
イエアメガエルを含む多くのカエルは、外敵から身を守るため、皮膚の表面から粘液を出します。この粘液には、弱い毒素が含まれていることがあります。
人間にとって命に関わるような強い毒ではありませんが、カエルを触った手でうっかり目や口、あるいは傷口などをこすってしまうと、ヒリヒリとした痛みや炎症を引き起こす可能性があります。
特に小さなお子さんや、他のペット(犬や猫など)がいるご家庭では、誤ってカエルに触れたり、舐めたりしないよう、ケージの管理や触れ合い後の手洗いを徹底することが非常に重要です。
フンの処理・衛生管理が必要
食べたものは、もちろんフンとして排泄されます。体の大きさの割に、しっかりとした量のフンをすることもあります。
このフンをケージ内に放置しておくと、前述の「臭い」の原因になるだけでなく、高温多湿の環境下で雑菌が急速に繁殖し、カエル自身が不衛生な環境にさらされることになります。これは、カエルのデリケートな皮膚病の原因や、体調不良につながる大きなリスクとなります。健康を守るためにも、フンは見つけたらこまめに取り除く衛生管理が欠かせません。

消化不良のリスク
イエアメガエルは非常に食欲旺盛で、動くものにはすぐに反応し、目の前にあるだけ食べてしまうことがあります。しかし、一度に食べ過ぎてしまうと、うまく消化ができずに体調を崩し、吐き戻したり、最悪の場合、消化管に負担がかかり病気になったりすることがあります。
また、消化不良は、飼育温度が低い状態(カエルの代謝が落ちている状態)で餌を与えた場合にも起こりやすいです。肥満にもなりやすいため、適切な量と頻度を見極める給餌量のコントロールは、飼主さんの重要な役目です。
適切な環境維持が必須
イエアメガエルは変温動物であり、自分では体温を調節できません。そのため、生息地のオーストラリアやニューギニアの気候に合わせ、飼育ケージ内の温度と湿度を一年を通して一定に保つ必要があります。特に日本の冬は寒すぎるため、パネルヒーターや保温球といった保温器具を使い、カエルが活動できる温度(約25度)を維持し続けることが必須です。
逆に夏場も油断できず、閉め切った部屋ではケージ内が30度を大きく超える高温になり、熱中症で命を落とす危険があります。エアコンでの室温管理など、年間を通した環境維持が求められます。
イエアメガエル飼育のデメリットを減らす工夫

ここまで読むと少し不安になってしまったかもしれませんが、ご安心ください。これらのデメリットは、日々のちょっとした工夫や準備で、しっかり対策することができます。快適なイエアメガエルライフを送るための工夫をご紹介します。
適切な設備で温度・湿度を安定維持
イエアメガエルにとって最も大切なのが、温度と湿度の管理です。特に冬場の寒さは大敵なので、ケージ全体を温めるパネルヒーターや、保温球を設置しましょう。温度が上がりすぎないよう、サーモスタットという自動で温度を調節してくれる機械につなぐと安心です。
密閉性の高いケージで脱走を防止
脱走対策は、ケージ選びから始まります。イエアメガエルを飼育する場合は、必ず蓋がしっかりとロックできる、爬虫類・両生類専用のケージを選びましょう。ガラス製のケージは隙間が少なく、おすすめです。日々のお世話の後、蓋を閉めるときは「カチッ」と音がするまで確実にロックする習慣をつけることが大切です。
おすすめはこの爬虫類ケージ「GEX エキゾテラ グラステラリウム 4530」です。
このケージは、イエアメガエルのような活発なカエルを飼うのにとても適しています。ガラス製で視界がクリアなため、観察を楽しみながら飼育できるのが魅力です。さらに、前面のドアが開閉式になっているので、毎日の餌やりや掃除がしやすく、ストレスなくメンテナンスが行えます。
また、しっかりとしたロック機能がついており、脱走防止の面でも安心です。トップカバーがメッシュ構造になっているため、通気性も抜群で、湿度や温度の調整がしやすい点もポイントです。サイズも扱いやすく、スペースを取りすぎないため、家庭での飼育にもぴったりです。
餌の管理で消化不良を予防
食いしん坊なイエアメガエルの健康を守るため、餌の量と頻度を管理しましょう。まだ小さい幼体のうちは毎日、体がしっかりしてきた大人のカエルには2~3日に一度、適量を与えます。食べ残した餌は、ケージが汚れる原因にもなるため、すぐに取り出すようにしてください。
設置場所の配慮で鳴き声に対応
もしオスの鳴き声が気になる場合、ケージの設置場所を工夫することで、音を和らげることができます。例えば、寝室から離れたリビングなどにケージを置くだけでも、夜間の鳴き声が気になりにくくなります。また、ケージの周りを防音性の高い素材で囲うことも一つの方法です。
定期的な清掃と消臭対策で臭いを解消
臭いの問題は、こまめな掃除で解決できます。フンは見つけたらその都度取り除き、清潔な状態を保ちましょう。床材の種類にもよりますが、定期的な交換や洗浄も必要です。
| 掃除の種類 | 頻度の目安 | 掃除の内容 |
| 日常の掃除 | 毎日 | フンや食べ残しの除去、水入れの水交換。 |
| 定期的な掃除 | 1ヶ月に1回程度 | 床材の全交換、ケージ内の拭き掃除。 |
| 大掃除 | 3ヶ月~半年に1回 | ケージ全体の丸洗い、消毒(ペット用の安全なもの)。 |
触れ合い方を守り、徹底した衛生管理
イエアメガエルの皮膚はデリケートです。また、粘液に弱い毒があることも忘れてはいけません。触れ合う場合は、人間の体温でカエルが火傷しないよう、手を冷たい水で濡らしてから、ごく短時間にするのが理想です。そして、カエルを触った後は、必ず石鹸で丁寧に手を洗うことを徹底してください。
イエアメガエル飼育のデメリット まとめ

イエアメガエルの飼育には、生き餌の管理や鳴き声、衛生面など、いくつか知っておくべき「デメリット」があります。しかし、その一つ一つは、なぜそうなるのかを理解し、あらかじめ適切な準備と工夫をすることで、ほとんどが解決できる問題です。
デメリットをしっかりと受け止めた上で、それを上回るイエアメガエルの「ずんぐりむっくりな可愛らしさ」や「ゆったりとした仕草」に癒される生活は、とても豊かで楽しいものですよ。この記事が、あなたの素敵なカエルライフの第一歩になれば幸いです。
両生類の関連記事はこちらから!!
アカハライモリが餌を食べない理由とは?原因と解決策を徹底解説!










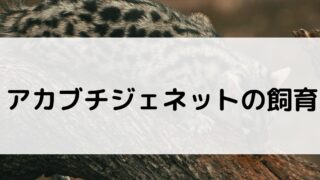



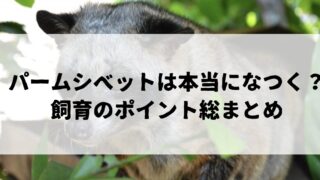







コメント