「小さくて可愛いから」「SNSで見て憧れたから」
そんな理由でリスを飼いたいと思っている方も多いのではないでしょうか?
しかし、いざ飼ってみると「思っていたより懐かない」「夜中にうるさい」「お金が意外とかかる」など、さまざまなギャップに戸惑う声も少なくありません。

この記事では、リスを飼ううえで事前に知っておくべき12のデメリットを詳しく解説します。
✔ リスは懐きにくく、人との距離感に注意が必要
✔ タイガー化など凶暴化する時期もある
✔ 活発な性格ゆえの脱走リスクや騒音の問題
✔ エキゾチックアニマルならではの医療・費用の課題
リスの魅力だけでなく現実的なデメリットにも目を向けることで、「思っていたのと違った…」という後悔を防ぐことができます。
可愛いだけじゃない、“本当のリスの姿”を知り、後悔しないペット選びをしましょう。
リスを飼うデメリット 12選

② 凶暴になる時期がある(タイガー化)
③ 運動量が非常に多い
④ 脱走しやすい
⑤ 長時間の留守番に向かない
⑥ 鳴き声や足音がうるさいことも
⑦ トイレを覚えない
⑧ かじり癖がある
⑨ エサ代や飼育用品のコストがかかる
⑩ ケガや体調不良に気づきにくい
11. リスを診られる動物病院が少ない
12. 寿命が短い
⓵ 懐きにくいことがある
リスは本来野生の動物であり、犬や猫のように人に対して強く懐くことはあまりありません。
個体差が非常に大きく、人に慣れやすい子もいれば、なかなか距離を縮めてくれない子もいます。
特に初めてペットとしてリスを迎える方にとっては、スキンシップを取ることが難しいと感じる場面が多くあるかもしれません。また、突然の動きや音に敏感なため、飼い主が手を差し出しただけでも驚いて逃げてしまうことがあります。
リスとの信頼関係を築くには、焦らず時間をかけて接する姿勢が重要です。触れ合いを楽しみにしていた人にとっては、その距離感に戸惑い、思っていたようなペットライフと違うと感じることもあるでしょう。
飼育舎のリスさんは仲良くみえる@さいたま市りすの家 pic.twitter.com/OisRlC52MH
— SYZW (@nichimosachimo) June 29, 2025
② 凶暴になる時期がある(タイガー化)
特に成長期や発情期には、性格が一時的に攻撃的になる「タイガー化」と呼ばれる現象が見られます。
えっほ、えっほ、タイガー期のシマリスは怖いって伝えなきゃ。 pic.twitter.com/dMLeYcyv7I
— シマリスのしまとあめ (@shimaame_22) April 12, 2025
これはホルモンバランスの変化や、成長に伴う縄張り意識の高まりが原因とされ、飼い主に対しても急に噛みついたり、威嚇の声を出すなど、普段とは明らかに異なる行動を取るようになることがあります。タイガー化の時期には、普段は大人しいリスであっても手を出すことが危険になるため、無理に触ろうとせず、距離を保って見守ることが大切です。
また、この時期の行動を理解せずに驚いたり叱ったりすると、リスとの信頼関係が崩れてしまうこともあるため、事前に知識を持っておくことが重要です。
タイガー化についてはこちらの記事を参考にしてください。

③ 運動量が非常に多い
リスは非常に活発な動物で、野生では木の上を走り回ったり、長距離を移動して餌を探す習性があります。
そのため、家庭での飼育においても豊富な運動量が必要です。
狭いケージ内だけで生活させると、十分な運動ができず、ストレスが溜まりやすくなります。
ストレスが慢性化すると、毛をむしる、常同行動(同じ動きを繰り返す)をするなどの異常行動につながる恐れがあります。
また、運動不足は肥満や骨の弱化などの健康トラブルも引き起こしかねません。
毎日たっぷり動けるスペースを確保し、回し車や止まり木、登れるおもちゃなどを用意して、飽きずに体を動かせる環境を整えてあげることが大切です。
できれば毎日、一定時間ケージの外で遊ばせる“放し飼いタイム”を設けるのも理想的です。
これはめっちゃ走るシマリス pic.twitter.com/B5a3dltXkF
— しんおう (@shinou_zero) January 3, 2024
④ 脱走しやすい
リスは体が小さく非常に素早い動きをするため、ちょっとしたケージの隙間や網目、開けたドアの一瞬の油断などから簡単に脱走してしまいます。
特に放し飼い中や掃除中など、人の注意がそれた瞬間を狙って逃げ出すこともあります。
一度逃げると家具の下や壁の隙間、配線の裏など狭くて入りにくい場所に隠れてしまい、捕まえるのが非常に困難になります。
運悪くベランダや玄関から外へ出てしまうと、そのまま戻ってこないケースも少なくありません。
脱走を防ぐためには、ケージの強度と構造に気をつけ、施錠可能な扉を使う、放し飼い時は必ず閉じた部屋で行うなど、徹底した対策が必要です。
また、万一の脱走に備えて、名前や連絡先を書いた小さなタグを装着しておくのもおすすめです。
⑤ 長時間の留守番に向かない
リスはデリケートな動物で、環境の変化や気温の変動に弱く、温度管理をしっかり行う必要があります。
エアコンやヒーターを使用して適切な室温を維持することが重要ですが、これを長時間放置したままにするのは危険です。
また、リスの中には飼い主とのスキンシップを好み、毎日構ってほしいと感じる個体もいます。
そういったリスにとっては、長時間の放置は大きなストレスとなり、食欲不振や体調不良につながることもあります。
出張や仕事が忙しくて家を空ける時間が長い方には、リスの飼育はあまり向いていない可能性があります。
どうしても留守にしがちな場合は、家族と協力したり、ペットシッターを利用するなどの工夫が必要です。
⑥ 鳴き声や足音がうるさいことも
リスは本来、昼行性または薄明薄暮性(朝夕に活動的)であることが多いですが、飼育環境によっては夜間に活発になることもあります。
特に夜間や早朝になると、ケージ内で元気に動き回ったり、止まり木や回し車を激しく使ったりして、予想以上の音を立てることがあります。
加えて、リスの鳴き声は高音で鋭いため、静かな部屋では思った以上に響いてしまうことも。
アパートやマンションのように隣人との距離が近い住環境では、騒音トラブルに発展する可能性もあるため、防音対策や活動時間に合わせた配慮が求められます。
防音性の高いケージを選ぶ、設置場所を工夫する、厚手の布をかぶせるなど、音への対策を事前に行っておくことが大切です。
【音量注意】隣のシマリスが回し車で走っていてうるさいです…
オヤツでもらったおリンゴを、回し車に頭をぶつけながら隠すシマリス。#シマリス#シマリスのしろっぷ pic.twitter.com/eCux0yGLj1
— トロ(もふアカ) (@yztoroyz14) November 8, 2020
⑦ トイレを覚えない
リスは一般的にトイレのしつけがほとんどできない動物です。
犬や猫のように特定の場所で排泄を覚える習性がないため、ケージの中でも、放し飼いにしている最中でも、思わぬ場所で排泄してしまうことがよくあります。
特に放し飼いの際は、床、家具の上、カーテンの裏など、さまざまな場所が排泄の対象となるため、掃除が非常に大変です。
また、排泄物のニオイも気になるため、こまめな清掃と換気が欠かせません。
消臭スプレーや吸収性の高いペットシーツを使うなどの工夫も必要です。
トイレの位置を固定して設置してみる、排泄しやすいタイミングでそこに誘導するなどの訓練もありますが、確実な成功を期待するのは難しいため、飼い主側が割り切って対応できるかどうかが重要です。
⑧ かじり癖がある

リスの歯は一生伸び続けるため、自然と物をかじる習性があります。
これは歯の伸びすぎを防ぐための本能的な行動であり、止めることはできません。
ケージ内にかじり木などの専用グッズを用意しておくことは基本ですが、それでも放し飼い中に家具の角、木製の棚、さらには電源コードなどをかじってしまう危険があります。
特にコード類をかじると感電や火災のリスクがあり、非常に危険です。
また、小さな異物をかじって飲み込んでしまうと、消化器官を傷つけるおそれもあります。
安全なかじりアイテムを複数設置し、放し飼い時にはリスの行動を常に見守ることが求められます。
可能であれば放し飼い専用のスペースを作り、かじってほしくない物は事前に片付けておくなどの環境整備が欠かせません。
⑨ エサ代や飼育用品のコストがかかる
リスの飼育には見た目以上にお金がかかります。
まず、主食となるリス専用のペレットや木の実、果物、野菜など、栄養バランスに配慮した多様なフードを準備する必要があります。
これに加え、歯の伸びすぎを防ぐためのかじり木、運動不足を解消するための回し車や登り木、止まり木などの遊具も揃えなければなりません。
また、汚れた床材の交換やおもちゃの劣化による買い替えなど、継続的なメンテナンス費用もかかります。
さらに、リスの健康を維持するためには、時折健康診断や病気の際の治療も必要になり、これらの医療費も考慮しておく必要があります。
一見小動物でコストが抑えられるように思えるかもしれませんが、長期的には意外と出費がかさむため、事前にしっかりと資金計画を立てることが重要です。
⑩ ケガや体調不良に気づきにくい
リスは非常に繊細な体を持ち、さらに本能的に体調の悪さを隠す習性があります。
これは野生下で弱っていることを悟られると天敵に狙われやすくなるためですが、飼育下においてもその傾向は変わりません。
そのため、外見上は元気に見えても、実際には体の中で異常が進行していることがあります。
たとえば食欲不振や排泄の変化、活動量の低下といった微妙な変化を見逃すと、気づいた時にはすでに重症化していることもあります。
特に内臓系の病気や骨折、歯のトラブルなどは見た目だけでは判断しにくく、定期的な観察と注意深いチェックが必要です。
小さな変化を見逃さないためにも、日々の様子を記録する習慣をつけたり、少しでも異変を感じたらすぐに動物病院で診てもらう体制を整えておくことが大切です。
11. リスを診られる動物病院が少ない
リスは一般的な犬猫と異なり「エキゾチックアニマル」に分類されるため、すべての動物病院で診察してもらえるわけではありません。
専門的な知識や設備を必要とするため、リスを診ることができる獣医師は限られており、対応できる病院の数も少ないのが現状です。
特に地方に住んでいる場合は、最寄りの病院までかなりの距離があることも珍しくなく、急な体調不良やケガが起きた際にすぐに対応できないリスクがあります。
さらに、エキゾチックアニマルを専門に扱う病院は診察料や検査費用が高めになる傾向があるため、費用面での準備も重要です。
リスを迎える前には、あらかじめ近隣に診てもらえる病院があるかどうかを調べておき、できれば一度事前に相談や見学をしておくことが安心につながります。
12. 寿命が短い
リスの寿命は種類や飼育環境にもよりますが、おおよそ5〜10年程度とされています。
小型の哺乳類としては一般的な寿命ですが、犬や猫と比べるとやや短命な印象を受ける人もいるかもしれません。
特に毎日お世話をし、愛着が湧いたペットとの別れは非常につらいもので、数年でその瞬間が訪れてしまうことを理解しておく必要があります。
また、リスは体が小さいため、ちょっとした体調の変化が命に関わる事態に繋がることもあり、病気の進行も速い傾向があります。
飼い主には日々の健康観察と早期対応が求められます。
寿命の短さを受け入れたうえで、その限られた時間をどれだけ豊かにしてあげられるかが、飼育の大きなポイントとなります。
リスを飼うデメリットを軽減するために

・信頼できるサポート体制を整える
・飼育スペースと生活スタイルの見直し
・長期的なコストを把握しておく
・掃除しやすいレイアウトにする
・リスを飼うデメリット まとめ
飼う前に十分なリサーチを
リスは一般的なペットとは異なる習性や飼育条件を持っているため、事前の情報収集は非常に重要です。
飼育本や信頼性のあるウェブサイトだけでなく、実際にリスを飼っている経験者のブログやSNS投稿、動画なども参考にすると、より現実的な飼育の様子をイメージしやすくなります。
こちらの本は基本情報から接し方など、かなり詳しく書いてあるのでおすすめです。
また、リスの種類ごとに性格や必要なケアが異なるため、迎える予定の種類に特化した情報を集めることが大切です。

飼育の難しさや困難な点も含めて客観的に理解し、「かわいい」だけで安易に決めない冷静な判断が求められます。
リスの本能的な行動や健康管理、必要なグッズの種類や安全対策などを事前に知っておくことで、飼ってから後悔するリスクを大幅に減らすことができます。
信頼できるサポート体制を整える
リスの飼育では、困ったときや異常を感じたときに相談できる信頼できるサポート体制があると非常に心強いです。
特にエキゾチックアニマルに対応している動物病院を見つけておくことは最優先事項の一つです。
通常の動物病院ではリスを診てもらえないこともあるため、診療可能な病院を事前に調べておき、可能であれば一度受診しておくと安心です。
また、リスを飼っている仲間やコミュニティに参加することで、日常のちょっとした疑問やトラブルに対する情報交換ができます。
SNSのグループ、地域のエキゾチックアニマルクラブ、飼育者向けのフォーラムなど、さまざまな交流の場があります。
ひとりで悩まずに、サポートを受けられる環境を作っておくことが、長く楽しく飼い続けるための大きな助けになります。
飼育スペースと生活スタイルの見直し

リスは非常に活発な動物であり、狭いケージや限られたスペースだけではストレスが溜まりやすくなります。
そのため、自宅の広さや間取りがリスの運動や生活に適しているかを事前に確認することが重要です。
また、家族構成や生活リズムも影響します。
たとえば、小さな子どもが頻繁に騒がしくしている環境や、日中誰も家にいない時間が長い家庭では、リスが安心して過ごすことが難しい場合があります。
リスが静かに休める場所を確保しつつ、毎日の遊びや運動も考慮に入れたスペース設計が求められます。
放し飼いの時間を安全に楽しめるように、部屋の安全対策(コードを隠す、隙間をふさぐなど)も必要です。
生活スタイルがリスの飼育に合っているかを見直し、必要があれば調整することが、長く健康的に飼い続けるうえで大きなポイントになります。
長期的なコストを把握しておく
リスの飼育には、初期費用だけでなく長期間にわたって継続的にかかるランニングコストを把握しておく必要があります。
エサ代はもちろん、床材やトイレシート、かじり木、回し車といった消耗品も定期的に交換が必要です。
さらに、病気やけがに備えて、定期的な健康診断や予防的な治療費、緊急時の通院費用も想定しておくべきです。
特にエキゾチックアニマル対応の動物病院では診察料が高額になることが多く、思わぬ出費に備えておくことが大切です。
また、ペット保険に加入するかどうかも含めて、長期的な視点での資金計画を立てることが、安心して飼育を続けるための基盤となります。
家計に無理のない範囲でリスとの生活を楽しむために、事前にコストをシミュレーションしておくことをおすすめします。
掃除しやすいレイアウトにする
リスはトイレの失敗や餌の散らかしが日常的にあるため、掃除のしやすさは飼育の快適さを大きく左右します。
床材は汚れを吸収しやすく、交換が簡単な素材を選ぶことがポイントです。
また、ケージ内の構造にも配慮し、排泄物が溜まりにくい位置にトイレを設置する、食事スペースを清潔に保てるように仕切りを使うなどの工夫が役立ちます。
さらに、放し飼い時に備えて、家具の下にトレーを敷いたり、汚れてもすぐ拭ける素材のマットを敷くなど、家全体のレイアウトも見直しておくと日々の掃除が格段に楽になります。
リスを飼うデメリット まとめ

リスは可愛らしい反面、飼育には多くの配慮と手間が必要です。
「リスを飼うデメリット」を正しく理解したうえで、自分のライフスタイルや環境に合っているかを冷静に判断しましょう。
飼う前に十分な準備と覚悟をもって迎え入れれば、リスとの生活はきっと充実したものになるはずです。











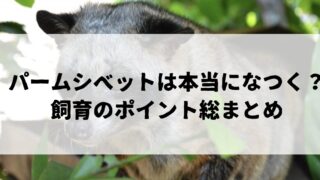






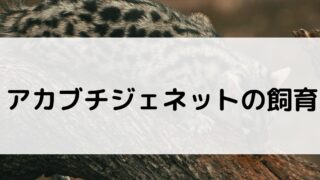



コメント