サワガニが餌を食べない原因とは?おすすめの餌とダメなもの
大切に飼育しているサワガニが、ある日を境にぷっつりと餌を食べなくなると、飼い主としては「病気なのだろうか?」「このまま弱って死んでしまったらどうしよう」と、心穏やかではいられなくなりますよね。その不安な気持ちは、生き物を大切に想う飼育者であれば誰もが経験するものです。
サワガニが餌を食べなくなる背景には、実はサワガニ自身の繊細な生態が深く関わっています。サワガニは、急な環境の変化や水質の悪化に非常に敏感な生き物であり、食欲不振はサワガニが発する重要な「サイン」なのです。そのサインを正しく読み解き、適切な対処をしてあげることこそ、飼育者に求められる役割と言えるでしょう。
この記事では、サワガニが餌を食べない時に考えられるあらゆる原因を網羅的に解説し、それぞれの状況に合わせた具体的な対処法、さらには日頃から与えるべきおすすめの餌や、食欲不振を未然に防ぐための予防策まで、徹底的に深掘りしていきます。この記事を最後まで読めば、あなたのサワガニがなぜ餌を食べないのかという疑問が解消され、再び元気に餌を食べる姿を取り戻すための具体的な道筋が見えるはずです。
サワガニが餌を食べない? ダメなもの

サワガニが餌を食べないという深刻な問題に直面した際、多くの飼育者はすぐに対処法を探しがちです。しかし、その前にまず立ち止まり、「サワガニの食性」や「正しい餌の与え方」という基本中の基本を再確認することが、問題解決への一番の近道となります。普段の食事管理がいかにサワガニの健康と食欲に直結しているか、その重要性について詳しく見ていきましょう。
サワガニの餌は?
サワガニは「雑食性」で、自然界では水生昆虫、藻類、小さな生き物の死骸など、何でも食べます。この食性を飼育下で再現するため、栄養バランスが考慮された市販の「ザリガニの餌」や「カニの餌」を主食に据えるのが最も手軽で安心です。
これらはサワガニが必要とするタンパク質やカルシウムなどがバランス良く配合されています。さらに、時々おやつとして茹でた煮干しやシラス、少量の野菜を与えることで、食事に変化が生まれ、サワガニも飽きずに食べてくれます。
サワガニの餌の頻度
餌を与える頻度は、毎日あげる必要はありません。2日から3日に1回のペースが理想的です。
サワガニはゆっくりと時間をかけて消化するため、毎日餌を与えると消化器官に負担がかかり、食べ残しが増えて水質を悪化させる原因にもなります。個体の大きさや季節による活動量の変化(夏は活発、冬は鈍くなる)を見ながら、最適な間隔を見つけてあげましょう。
餌のタイミングとあげ方
サワガニは夜行性の傾向が強いため、活動が活発になる夜、部屋が暗くなる少し前に餌を与えるのが最も効果的です。
昼間は物陰に隠れていることが多く、餌に気づかないこともあります。餌は、ピンセットでサワガニの隠れ家の近くにそっと置いてあげると、臆病な個体でも安心して食べることができます。
サワガニの餌でダメなもの
雑食性で何でも食べるイメージのサワガニですが、人間の食生活の中にあるものには、サワガニの小さな体にとって「毒」となり得るものが数多く存在します。安易に与えると、消化不良どころか、命に関わる事態を引き起こしかねないため、正しい知識を持つことが不可欠です。
特に人間のために調理・加工された食品は、ほぼ全てがNGと考えてください。これらに含まれる過剰な塩分、油分、糖分、そして多種多様な化学調味料や保存料といった添加物は、サワガニの繊細な内臓では分解・排出することができず、深刻なダメージを与えてしまいます。
これらの知識は、サワガニの健康を守るための最低限のルールです。良かれと思ってしたことが、逆にサワガニを苦しめる結果にならないよう、細心の注意を払いましょう。
サワガニの餌になる家にあるもの

専用の餌を切らしてしまった時や、食事に変化をつけたい時に、家にある食材が役立つことがあります。ただし、どんなものでも良いわけではなく、選び方と与え方には注意が必要です。
キャベツ
キャベツは多くのサワガニが好む野菜です。食物繊維やビタミンが豊富ですが、与える際には必ず注意点があります。それは残留農薬の可能性です。
外側の葉は特に農薬が付着している可能性が高いため、よく水で洗い流すか、内側のきれいな葉を選んで与えましょう。生のままでも食べますが、消化のしやすさを考えると、数秒さっと茹でて冷ましたものを与えるのがより親切です。ごく小さなひとかけらで十分な量です。
かつおぶし
かつおぶしの強い香りは、サワガニの食欲を強力に刺激します。普段食が細い個体や、餌に飽きてしまった個体に試してみる価値は十分にあります。
ただし、スーパーで一般的に売られているかつおぶしには、風味を増すための塩分や、カビを防ぐための処理がされている場合があります。理想は、ペット用や出汁用に販売されている「塩分無添加」の製品を選ぶことです。もし手元にない場合は、ごくごく少量、指でひとつまみ程度に留めてください。
その他の野菜
キャベツ以外にも、サワガニが食べられる野菜はいくつかあります。代表的なのはニンジン、カボチャ、ブロッコリーの芯、トウモロコシなどです。
これらの野菜に共通する与え方のポイントは、「加熱して柔らかくし、十分に冷ます」ことです。硬い生のままでは食べることができず、消化にも悪いです。
ニンジンやカボチャは自然な甘みがあり、特に好む個体が多いようです。いずれの野菜も、主食の合間に与えるおやつとして、栄養の偏りを補う目的で少量与えるのが賢明な使い方です。
我が家のサワガニの餌


参考までに、筆者が自宅で実践している餌の与え方の一つをご紹介します。
我が家では、少し変わった試みとして、「生きたメダカ」を餌として与えています。 具体的には、サワガニを飼育している水槽に、餌用のメダカを数匹一緒に泳がせておくのです。サワガニは夜行性なので、私たちが寝ている夜の間に活発に動き回り、お腹が空いたタイミングでメダカを自分で捕まえて食べています。


この「活き餌」の方法には、メリットとデメリットがあります。
- メリット: 食べ残しが一切出ないため、水質が悪化しにくい点です。人工飼料のように、水中でふやけて水を汚す心配がありません。
- デメリット: サワガニがすぐにメダカを捕まえられるとは限らず、捕食までに時間がかかることもあります。
もちろん、メダカだけでは栄養が偏ってしまう可能性があるため、基本的には市販の専用フードもしっかりと与え、栄養バランスを整えることが大切です。活き餌は、あくまで食事のバリエーションの一つ、あるいはサワガニの狩猟本能を刺激するための補助的な食事と考えています。
サワガニが餌を食べないときの主な原因とは?

日々の食事管理を徹底していても、サワガニが突然餌を食べなくなることは起こり得ます。そんな時、パニックにならずに冷静に原因を探ることが問題解決の第一歩です。「サワガニが餌を食べない」というサインの裏に隠された、7つの主な原因を一つずつ詳しく解説していきます。ご自身の飼育環境と照らし合わせ、原因を特定するヒントにしてください。
脱皮前後で餌を食べないことがある
飼育下のサワガニが餌を食べなくなる原因として、最も頻繁にみられ、かつ最も心配のいらない理由が「脱皮」の準備期間に入ったことです。甲殻類であるサワガニは、成長するために古い殻を脱ぎ捨てる「脱皮」を繰り返します。
脱皮の数日前から、サワガニは体内の生理的な変化に対応するため、すべてのエネルギーを脱皮の準備に集中させます。そのため、消化にエネルギーを使う食事を一切受け付けなくなります。同時に、外敵から身を守るために物陰に隠れてじっと動かなくなるため、飼育者からは「病気でぐったりしている」ように見えてしまうのです。これは、サワガニが次のステージへ進むための正常な生理現象であり、温かく見守ってあげましょう。

水質の悪化がストレスになっている
サワガニは「清流の指標生物」とも呼ばれるほど、きれいな水を好む生き物です。飼育水槽という閉鎖された環境では、餌の食べ残しやフン、脱皮の抜け殻などが分解される過程で、目に見えない有害物質が発生します。その代表が「アンモニア」です。アンモニアは非常に毒性が高く、わずかな濃度でもサワガニのエラにダメージを与え、体調を著しく悪化させます。
アンモニアが蓄積した水は、サワガニにとって猛毒のガスが充満した部屋にいるようなものです。このような劣悪な環境では、当然ながら食欲は湧きません。むしろ、体調不良から食欲不振に陥っている状態です。水の見た目が透明で透き通っていても、有害物質は溶け込んでいます。定期的な水換えを怠っている場合、食欲不振の原因が水質の悪化である可能性は非常に高いと言えるでしょう。
温度が低すぎる・高すぎる
サワガニは変温動物であり、自身の体温を周囲の温度に依存しています。そのため、飼育環境の水温はサワガニの活動レベル、すなわち代謝活動に直接的な影響を与えます。
水温が15℃を下回るような低温環境では、サワガニの体内の化学反応、つまり代謝活動全体がスローダウンします。これにより、消化酵素の働きも鈍くなり、食べ物を消化する能力が低下するため、本能的に食事を摂らなくなります。これは冬眠に近い状態で、エネルギー消費を最小限に抑えるための合理的な行動です。
逆に、水温が28℃を超えるような高水温はさらに危険です。サワガニは元来、水温の低い渓流に生息しているため、高温への耐性がありません。高水温はサワガニにとって極度のストレスとなり、人間でいう「夏バテ」や「熱中症」のような状態に陥ります。体力を著しく消耗し、ぐったりとして食欲どころではなくなってしまいます。
餌が合っていない・硬すぎる
人間にも食べ物の好みがあるように、サワガニにも個体による餌の好みがあります。今まで食べていた餌から、新しい種類の人工飼料に変えた途端に食べなくなったのであれば、単純にその餌の味や匂いが気に入らないのかもしれません。
また、物理的な「硬さ」も問題になることがあります。特に、小さな個体や、顎の力が弱ってきた老齢の個体にとっては、粒の大きな人工飼料は硬すぎて噛み砕くことができず、食べたくても食べられないという状況に陥っている可能性があります。餌を目の前にしても、少しついばむだけで諦めてしまうような素振りが見られる場合は、この原因を疑ってみるべきです。
環境の変化
サワガニは非常に臆病で、環境の変化に敏感な生き物です。飼育者にとっては些細な変化でも、サワガニにとっては生活の基盤を揺るがす大事件となり、強いストレスを感じることがあります。
例えば、新しい水槽への引っ越し、水槽内のレイアウトの大幅な変更、新しい隠れ家や石の追加、そして新しいサワガニの追加(同居)などが、その引き金になります。環境が大きく変わると、サワガニはまず身の安全を確保することを最優先します。周囲を警戒し、新しい環境に慣れるまでは、安心して食事を摂ることができなくなり、食欲不振に陥ってしまうのです。この「警戒モード」が解除されるまでには、数日から1週間以上かかることもあります。
夜行性のため日中は食べない
飼育しているサワガニの姿を日中に見ることが多い飼育者の場合、サワガニ本来の習性を見落としている可能性があります。前述の通り、サワガニは基本的に夜行性です。昼間は天敵の目を避けて物陰で息を潜め、安全な夜になってから活動を開始します。
もし、飼育者の生活サイクルに合わせて昼間の明るい時間帯に餌を与えていると、サワガニはまだ活動モードに入っていないため、餌に興味を示さないことが多々あります。その結果、飼育者は「餌を食べていない」と勘違いしてしまうのです。実際には、飼育者が見ていない夜間に、残された餌をこっそり食べているのかもしれません。
与えすぎや餌の腐敗
「元気に育ってほしい」という親心から、つい餌を頻繁に、そして多めに与えてしまうのは、初心者が陥りがちな失敗の一つです。しかし、これが逆効果になることがあります。常に水槽内に餌がある状態だと、サワガニは空腹を感じることがなくなり、いつでも食べられるという安心感から、かえって餌への執着を失ってしまいます。
また、水中に長時間放置された餌は、バクテリアによって分解が始まり、次第に腐敗していきます。人間が腐ったものを食べないのと同様に、サワガニも味や匂いで餌の鮮度を判断しており、古くなった餌や腐敗し始めた餌は口にしません。食べ残しを放置することは、水を汚すだけでなく、サワガニの食欲そのものを失わせる原因にもなるのです。

サワガニが餌を食べないときの対処法と改善策8選

原因のあたりがついたら、次はいよいよ具体的なアクションプランです。ここでは、それぞれの原因に対応した具体的な対処法と改善策を8つ、詳しく紹介します。「サワガニが餌を食べない」という状況を打破するために、飼育者として何ができるのか、一つずつ丁寧に見ていきましょう。
水替えの頻度と方法を見直す
水質の悪化が食欲不振の最も疑わしい原因である場合、即効性があり、かつ最も基本的な対処法が「水換え」です。有害物質が蓄積した古い水を、清浄な新しい水に入れ替えることで、サワガニのストレスを直接的に取り除くことができます。
手順としては、まず交換用の水を用意します。水道水をバケツなどに汲み、カルキ抜き剤を使って塩素を中和するか、一晩汲み置いて自然に塩素が抜けるのを待ちます。次に、その水の温度が、現在サワガニがいる水槽の水温とほぼ同じになるように調整します。この温度合わせを怠ると、水温の急変によるショックで、かえってサワガニにダメージを与えてしまいます。
準備ができたら、水槽全体の3分の1から半分程度の水を、ポンプやチューブを使って静かに抜き取ります。この時、底に溜まったフンやゴミも一緒に吸い出すと効率的です。そして、新しい水を水槽の壁面などに沿わせて、ゆっくりと注ぎ入れます。これにより、水質の急激な変化を和らげることができます。この基本的な水換えを、飼育環境に合わせて適切な頻度(フィルターなしなら2〜3日に1回、ありなら1週間に1回が目安)で継続することが、根本的な解決策であり、最高の予防策となります。
水温を25℃前後に保つ工夫
サワガニの食欲と健康は、適正な水温の維持にかかっていると言っても過言ではありません。水温を常に20℃から25℃の範囲に保つための具体的な工夫を紹介します。
まず、水槽用の水温計を必ず設置し、いつでも正確な水温が把握できるようにしておくことが大前提です。その上で、季節に応じた対策を講じます。
夏場の高水温対策としては、まず水槽を直射日光の当たらない、家の中で最も涼しく風通しの良い場所に置くことが基本です。その上で、最も確実な方法はエアコンによる室温管理ですが、それが難しい場合は、水槽用冷却ファンの導入を検討しましょう。ファンが水面に風を送ることで気化熱を促進し、水温を2〜4℃程度下げることができます。
冬場の低水温対策としては、観賞魚用のオートヒーターが有効です。自動で設定温度を保ってくれるため管理が楽ですが、サワガニがコードや本体をかじってしまう危険性を考慮し、必ずプラスチック製の安全カバーが付いた製品を選ぶようにしてください。
餌の種類を変えてみる(肉・野菜・市販品)
人間が毎日同じメニューだと飽きてしまうように、サワガニも同じ餌ばかりでは食が細くなることがあります。そんな時は、食事に変化をつけて、サワガニの食欲中枢を刺激してあげましょう。
現在、人工飼料のみを与えているのであれば、全く違う種類の餌を試してみる価値があります。例えば、動物性の餌として、香りが強く嗜好性が高い「乾燥エビ」や「塩抜きした煮干し」を少量与えてみます。また、植物性の餌として、さっと茹でて柔らかくした「ニンジン」や「カボチャ」の小片を与えてみるのも良いでしょう。
重要なのは、一度に大量に与えるのではなく、まずはサワガニが興味を示すかどうかを確認することです。ピンセットでつまんで鼻先に持っていき、反応を見るのも一つの方法です。様々な種類の餌を試す中で、あなたのサワガニの「大好物」が見つかるかもしれません。その好物を把握しておくことは、今後、再び食欲が落ちた時の切り札にもなります。
餌を小さく切って与える
「餌に興味は示すものの、うまく食べられていない」ように見える場合は、餌の物理的なサイズや硬さが原因かもしれません。この問題は、ほんの少しの工夫で解決できることがよくあります。
主食として与えている粒状の人工飼料が硬いと感じる場合は、与える直前に数分間、飼育水に浸してふやかしてあげましょう。これにより、芯まで柔らかくなり、小さな個体や力の弱い個体でも簡単に噛み砕くことができるようになります。
また、煮干しや乾燥エビ、野菜などを与える際も、サワガニの口の大きさを考慮し、ハサミなどで細かくカットしてから与えるのが親切です。目安として、サワガニの目の間隔くらいの大きさが、食べやすいサイズとされています。食べやすさを改善してあげるだけで、今まで諦めていた餌を喜んで食べるようになることは珍しくありません。
夜間に餌を与えるようにする
サワガニの本来の生活リズムを尊重することは、食欲を引き出す上で非常に効果的なアプローチです。もし現在、昼間の時間帯に餌を与えていて食いつきが悪いのであれば、ぜひ一度、夜間の給餌に切り替えてみてください。
最適なタイミングは、部屋の照明を消して周囲が暗くなり、サワガニが安心して活動を始められる時間帯です。飼育者が就寝する前などに、そっと水槽を覗き、サワガニの隠れ家の近くに餌を置いてあげます。日中の警戒心から解放されたサワガニは、本来の食欲を取り戻し、活発に餌を探し始める可能性が高いです。この方法で、「実は夜中にちゃんと食べていた」ということが判明することもよくあります。飼育者の生活リズムではなく、サワガニの生活リズムに寄り添うことが、信頼関係を築く第一歩です。
脱皮の兆候がないか観察する
何を試しても一向に餌を食べる気配がなく、物陰でじっとしている場合は、脱皮の準備期間に入っている可能性が濃厚です。この場合、飼育者がすべきことは「何もしないこと」、つまり「そっと見守ること」です。
脱皮前のサワガニは非常にデリケートであり、外部からの刺激は多大なストレスとなります。水槽を揺らしたり、無理に餌を口元に持っていったり、心配で体を触ったりする行為は、脱皮の成功率を下げてしまう危険性すらあります。
飼育者は、脱皮の兆候を注意深く観察することに徹しましょう。「甲羅と腹部の間の膜が白く伸びて見える」「体の色が全体的に白っぽくくすんでいる」「目が普段より奥に引っ込んでいるように見える」といったサインが見られたら、脱皮は間近です。無事に脱皮を終え、甲羅が硬化すれば、失われたエネルギーを補うために、また旺盛な食欲を見せてくれるはずです。
隔離して落ち着いた環境を作る
複数のサワガニを同じ水槽で飼育している場合、食欲不振の原因が個体間の力関係にあることも考えられます。気の強い個体が餌場を独占し、気の弱い個体が餌にありつけず、ストレスから食欲を失ってしまうのです。
このような様子が見られる場合は、餌を食べない個体を一時的に別の容器に「隔離」してあげることが非常に有効な対処法となります。市販の隔離ケース(サテライト水槽など)を本水槽に引っ掛けて使うか、小さなプラケースに元の水槽の水と隠れ家を入れて用意します。そこで一匹だけの落ち着いた環境を作り、安心して食事ができる状況を提供してあげるのです。ストレスから解放されることで、本来の食欲を取り戻すケースは少なくありません。元気を取り戻したら、元の水槽のレイアウトを見直し、隠れ家を増やすなどして、再発防止に努めましょう。
サワガニが餌を食べない? ダメなもの まとめ
愛らしいサワガニが餌を口にしなくなる姿は、飼育者にとって大きな不安の種です。しかし、その行動の裏には、脱皮という生命の営みから、水質や水温といった飼育環境からの静かな訴えまで、必ず何らかの理由が隠されています。
最も大切なのは、パニックにならずに、まずはこの記事で紹介したような原因の可能性を一つずつ冷静に探っていくことです。サワガニの様子を注意深く観察し、「なぜ食べてくれないのだろう?」とその心に寄り添う姿勢が、問題解決の鍵を握っています。
多くの場合、水換えや水温調整、餌の種類の変更といった、飼育環境の少しの見直しで、サワガニは驚くほど元気を取り戻し、再び旺盛な食欲を見せてくれます。「餌を食べない」という現象は、サワガニがあなたに送る「今の環境はちょっと合わないよ」というメッセージなのかもしれません。このサインを正しく受け取り、サワガニへの理解を深める機会と捉えることで、あなたの飼育スキルは向上し、サワガニとの絆はより一層強いものになるでしょう。











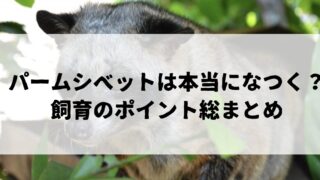



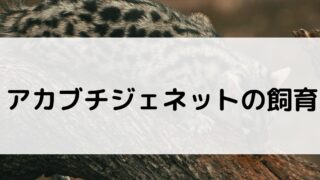










コメント