「シロハラインコって本当に人懐っこいの?」
「SNSでぴょこぴょこ動く可愛いシロハラインコを見たけど、実際の飼育は大変じゃないの?」
「飼ってみたいけど、後悔するようなことがあるって本当?」

そんな疑問を持っている方に向けて、本記事ではシロハラインコを飼って後悔する理由やデメリット、飼育における注意点を詳しく解説します。
見た目の可愛らしさやユニークな仕草から人気の高いシロハラインコ。
しかし、実際に飼ってみると「思っていたのと違った」と感じる方も少なくありません。
攻撃的な一面や大きな鳴き声、想像以上の世話の手間、30年にも及ぶ長寿命など、事前に知っておくべきことがたくさんあります。
正しい情報を知ったうえで、愛情を持って最後まで育てられるかどうかを見極めることが、後悔しない飼育への第一歩です。
この記事のポイント
✔ シロハラインコは攻撃的になったり噛んだりする個体もいる
✔ 鳴き声が大きく、集合住宅では騒音問題になりやすい
✔ 世話や掃除に手間がかかり、気軽に飼えるペットではない
✔ 長寿命で、30年近く責任を持つ覚悟が必要
✔ 獣医や販売店など、飼育環境の整備も不可欠
シロハラインコで後悔する人が多い理由とそのデメリットとは?

2. 攻撃的な時期がある(シャケ化)
3. 長寿命ゆえの覚悟が必要
4. 高額な購入費用と維持費に注意
5. 人に懐かない個体もいる
6. 毎日の掃除とお世話の手間がかかる
7. 環境の変化に弱い
8. 雛の入手が難しい
9. 鳥類専門の獣医が少ない
10. 他のペットとの相性が悪い場合がある
11. 多忙な人には向かない
12. 放鳥中の事故
鳴き声が大きい
シロハラインコはその愛らしい見た目とは裏腹に、非常に甲高く大きな鳴き声を発します。
特に朝夕の活動時間や飼い主が見えないときなどに「呼び鳴き」を繰り返す傾向があり、その音量は近隣住民にとって騒音と感じられることも少なくありません。
この鳴き声は壁の薄い集合住宅などではトラブルの原因となることもあり、ペット可の物件であっても苦情に発展するケースがあります。
また、ストレスや退屈を感じたときにも鳴き声が増えるため、環境やメンタルケアが重要です。
防音カーテンやケージカバーの導入、設置場所の工夫によってある程度の軽減は可能ですが、完全に音を抑えるのは困難です。
静かな住環境を必要とする方には向いていない場合もあるため、事前にこの特徴を理解しておくことが重要です。

攻撃的な時期がある(シャケ化)
シロハラインコは感情表現が非常に豊かで、特に興奮していたり、ストレスを感じているときに強く噛む時期があります。
このような攻撃的な行動は「シャケ化」とも呼ばれ、飼い主にとっては非常に困る問題行動の一つです。
噛まれると流血することもあり、特に子どもや高齢者の家庭では注意が必要です。
また、噛むことで自己主張をする癖がついてしまうと、改善するには長期的なトレーニングが必要になります。
華ちゃんが🐥シャケ化に…🙀#シロハラインコ pic.twitter.com/pfYKqunv4V
— 関根浩 (@birdhiroshis) December 29, 2022
信頼関係の構築はもちろん、正しいしつけ方法や専門家のアドバイスを取り入れながら、根気強く対応していく必要があります。
シャケ化についてはこちらを参考にしてください。

長寿命ゆえの覚悟が必要
シロハラインコの寿命は平均して25〜30年ほどと、一般的なペットの中でもかなり長い部類に入ります。
このため、一度迎え入れると人生の大半を共にする覚悟が必要になります。
特に進学、就職、結婚、転勤、引っ越し、育児、介護といったライフイベントの中でも、安定して飼育を続けられるかを真剣に考える必要があります。
また、自身の年齢とのバランスも重要で、高齢の方が飼い始める場合は「もし自分に何かあったときの引き取り手」まで想定しておかなければなりません。
鳥にとって飼い主は唯一の家族であり、途中で飼えなくなることは鳥の健康や精神にも大きな影響を与えます。
高額な購入費用と維持費に注意

シロハラインコはその希少性と人気の高さから、購入費用が非常に高額になる傾向があります。
一般的な相場でも20万円以上が多く、信頼できるブリーダーや専門店から健康な個体を迎えるとなると、さらに高値がつくことも珍しくありません。
加えて、飼育には初期費用以外にも多くの出費が伴います。
まず必須なのが大型のケージで、シロハラインコの活発な行動に対応するには、広々とした頑丈なものが求められます。
それに加えて、止まり木や巣箱、自然木でできたおもちゃ、羽を傷めない専用の餌入れ、水入れなども必要です。
さらに、安全性の高いペレットやフルーツ、サプリメントといった食事面の出費も日常的に発生します。
年に1~2回の健康診断やワクチン、体調不良時の通院・治療費も加えると、年間の維持費は数万円から十数万円にのぼることもあり、経済的な負担は決して小さくありません。
特に鳥類を診られる専門の動物病院は限られているため、遠方への通院が必要な場合は交通費や時間の負担も加わります。
シロハラインコは寿命が25〜30年と非常に長いため、短期的な出費ではなく、30年というスパンでのライフプランと経済設計が求められます。
結婚・出産・転職・老後といった人生の変化にも耐えられる金銭的な余裕があるかどうかをよく考慮し、「かわいいから」という理由だけでなく、経済的にも責任を持って迎えられるかどうかの判断が重要です。

人に懐かない個体もいる
シロハラインコは一般的には好奇心旺盛で人懐っこい性格をしているといわれていますが、実際には個体差が非常に大きく、すべての個体が人に慣れるとは限りません。
毎日丁寧に声をかけたり、手から餌を与えたりといった愛情表現を続けても、警戒心が強くなかなか近づいてくれない個体もいます。
無理にスキンシップを取ろうとすると、恐怖や不信感を与えてしまい逆効果になることも。特に野性味の強い個体では、長期間かけて信頼関係を築く必要があるため、根気と時間、そして鳥の個性を受け入れる柔軟さが求められます。
懐く個体でも機嫌や気分で態度が変わることがあり、「いつでもベタ慣れ」という期待は抱かない方が良いでしょう。
なつかない場合についてはこちらを参考にしてください。

毎日の掃除とお世話の手間がかかる
シロハラインコは活発に動き回るため、ケージ内外の汚れは日々溜まっていきます。
餌をくちばしで撒き散らす、フンの量が多い、羽が頻繁に抜けるなど、清掃が必要な要素が多く、掃除の頻度は最低でも1日1回が望ましいとされています。
また、放鳥時にはフンの処理や、床や家具への噛みつき・破壊行動の対応も必要です。
加えて、餌や水の入れ替え、おもちゃの点検・交換、日々の健康観察などの手間も発生し、決して「簡単に飼える鳥」ではありません。
忙しい社会人や不規則な生活をしている人にとっては、毎日の手入れが大きな負担になることもあるため、自分の生活スタイルに本当に合っているか慎重に判断する必要があります。
環境の変化に弱い
シロハラインコは非常に繊細な気質を持っており、住環境や生活リズムのちょっとした変化にも敏感に反応します。
例えば、ケージの場所を少し動かしただけでも不安になったり、部屋の照明や温度の変化、家具の配置換えなどでもストレスを感じることがあります。
また、飼い主の外出や旅行による不在も強い不安要素となり、寂しさから「呼び鳴き」が増えたり、羽を自ら抜いてしまう「毛引き症」に発展するケースも報告されています。
特に一羽で飼っている場合、日中の孤独を強く感じやすく、精神的な健康を保つには放鳥時間の確保や声かけ、知育玩具などによる刺激が欠かせません。
こうしたメンタルケアを怠ると、ストレスから食欲不振や攻撃的な行動につながる可能性もあるため、常に飼い主との信頼関係と安心できる生活環境の維持が必要不可欠です。
雛の入手が難しい
シロハラインコは国内での繁殖数が少なく、ペットショップで頻繁に見かける鳥ではありません。
そのため、健康で性格の良い雛を入手しようとすると、信頼できるブリーダーを見つけるのが重要なポイントとなります。
しかし、ブリーダーの数自体が限られており、場合によっては数ヶ月以上の予約待ちが発生することもあります。
また、悪質な業者による不適切な繁殖や管理状態の悪い環境で育った個体を避けるためにも、購入前には必ず見学や問い合わせを行い、親鳥の状態や飼育環境を確認することが重要です。
さらに、感染症や遺伝的疾患を防ぐための健康チェックが行われているかもチェックすべきポイントです。
こうした手間と時間がかかることを理解し、十分な準備をしたうえで迎え入れることが、長く健康に飼育するための第一歩となります。
鳥類専門の獣医が少ない
日本国内では、犬や猫に比べて鳥類を専門に診療できる動物病院は非常に限られています。
都市部であればまだ見つけやすいですが、地方ではそもそも鳥を診られる獣医が存在しない地域も珍しくありません。
そのため、シロハラインコのような繊細で体調の変化が分かりにくい鳥を飼う場合、万が一の時にすぐに受診できる病院を事前にリストアップしておく必要があります。
また、鳥類特有の病気や処置に詳しいかどうかも確認が必要で、定期的な健康診断や爪・くちばしのケアなども対応できるクリニックであるかも重要なチェックポイントです。
万一のときに慌てないよう、距離や診療時間、予約の可否なども含めて、あらかじめ十分に調査しておくことが安心につながります。
他のペットとの相性が悪い場合がある
シロハラインコは見た目が可愛く動きも活発なため、猫や犬などの他のペットにとっては「獲物」として認識されやすい傾向があります。
実際に、猫が鳥かごに飛びついたり、犬が放鳥中のインコを追いかけたりして、事故につながるケースも報告されています。
また、インコ自身にとっても他の動物の存在が強いストレス源になることがあり、落ち着いて過ごすことができず、体調を崩す原因になる場合もあります。
共に暮らすことが可能なケースもありますが、そのためには徹底した管理と距離の確保、そして双方の動物の性格を十分に見極めたうえで慎重に進める必要があります。
特に放鳥時は、ドアの閉鎖や監視の徹底など、安全管理を怠らないことが最優先です。
多忙な人には向かない
シロハラインコは非常に社交的な性格をしており、飼い主とのスキンシップや会話を通じたコミュニケーションを日常的に求める生き物です。
放鳥の時間や遊び相手が確保されていないと、精神的なストレスが溜まりやすく、それが原因で「呼び鳴き」や「毛引き」といった問題行動につながることもあります。
一人暮らしで朝から晩まで仕事に出ていたり、学業で長時間家を空ける方には、こうした要求に十分応えるのが難しい場面も多いでしょう。
また、日々のケアだけでなく、健康状態のチェックや感情の変化にも目を向ける必要があり、忙しい生活の中で細やかな対応を続けるには大きなエネルギーが必要です。
さらに、急な出張や長期の旅行などが頻繁にある場合には、世話を任せられる信頼できる人を確保しておく必要もあります。
こうした点を踏まえると、シロハラインコの飼育は時間的にも精神的にも余裕がある人に向いているといえます。
放鳥中の事故
シロハラインコは放鳥時に部屋中を自由に飛び回るため、家庭内のあらゆるものが危険の対象になり得ます。
たとえば、コンセントのコードをかじったり、観葉植物の葉を口にしたり、小さな金属やビニール片などを誤って飲み込んでしまうといった事故は実際に多く報告されています。
また、開いた窓やドアから外に飛び出してしまうリスクもあるため、放鳥前には必ず安全確認を行う必要があります。
加えて、調理中のキッチンや、湯を張ったバスタブ、トイレの便器など、意外な場所にも危険が潜んでいるため、放鳥中は必ず目を離さず、なるべく専用の安全なスペースを用意するのが望ましいです。
誤飲や怪我は一瞬の油断から起こるため、シロハラインコと暮らす上では、人間の赤ちゃんを育てるような徹底した安全対策が求められます。
朝はピーマンの種を🫑夜は桃を🍑おいちいね😋︎💕︎
ひっくり返って遊ぶのが好きなの可愛い過ぎるよ🐣🥰さし餌4回大変だけど吹っ飛ぶ可愛いらしさだ😊✨️#シロハラインコ #あんず日記 pic.twitter.com/6ZSMZ4F79q— MAME-REX💛 (@rex_mame) August 11, 2024
シロハラインコを飼って後悔しないために

・鳴き声・噛み癖への対策を事前に調べておく
・防音・掃除・放鳥など日々のケア体制を整える
・長期的に飼えるか家族やライフプランと相談する
・動物病院を確保しておく
・信頼できる販売店・里親制度を利用する
・シロハラインコを飼って後悔する理由とデメリット まとめ
購入前に体験飼育やブリーダー見学をしてみる
シロハラインコを飼う前に、実際に飼育している現場を見たり、ブリーダーと話をすることで、日常の世話がどれほど手間のかかるものかを体感できます。

ケージの掃除の頻度や、放鳥の重要性、餌の準備、鳴き声の大きさなど、ネット上の情報だけではわからないリアルな側面に触れることができます。
体験飼育では、鳥とどれだけの時間を共に過ごせるか、自分の生活スタイルと合っているか、具体的に確認することができるため、迎え入れる前の大きな判断材料になります。
また、見学の際には飼育環境や飼育者の管理意識にも注目し、清潔さや鳥の健康状態、ストレスの有無などを観察することが大切です。
こうした準備を経て、自分に本当に飼育ができるのか冷静に判断することが、後悔しないための第一歩になります。

鳴き声・噛み癖への対策を事前に調べておく
シロハラインコは感情表現が豊かで、嬉しいときや不安なときに鳴いたり噛んだりする行動が多く見られます。
特に「呼び鳴き」は非常に大きな音で鳴くため、集合住宅などでは近隣への配慮が欠かせません。
また、噛み癖についても、一度身についてしまうと改善に時間がかかるため、あらかじめその傾向や対応方法について知識を得ておくことが重要です。
たとえば、どういうときに噛むのか、噛んだときの正しい対応、しつけ方などを調べたり、実際に飼育している人の体験談を読むことで、現実的な対応策が見えてきます。
さらに、防音対策としては防音カーテンやケージカバーの活用、噛み癖対策としては噛んで良いおもちゃを与えるなど、事前に準備しておくことで飼育後のストレスやトラブルを軽減できます。
防音・掃除・放鳥など日々のケア体制を整える
シロハラインコの健康と快適な生活を維持するためには、日々のケア体制を万全に整えることが不可欠です。
放鳥の時間を確保するだけでなく、ケージの掃除、餌や水の交換、知育玩具の管理といった作業も日課としてスケジュールに組み込む必要があります。
特に防音対策は、近隣住民とのトラブルを避けるために重要で、防音カーテンやケージカバー、防音パネルなどを使って音の拡散を抑える工夫が求められます。
また、ケージの設置場所は人の目が届く静かな場所にし、温度や湿度の管理も重要です。
これらのケアを無理なく日常生活に取り入れるためには、あらかじめ時間配分や飼育スペースの整備を行い、習慣として生活リズムに組み込めるよう準備しておくことが成功のカギとなります。
飼育を始める前に必ず、本などで知識をつけるようにしましょう。

私のおすすめのインコ飼育本はこちらです。
長期的に飼えるか家族やライフプランと相談する
シロハラインコの寿命は25〜30年と非常に長く、家族の一員として長期間にわたり責任を持って世話をする必要があります。
そのため、今後の人生設計やライフステージの変化をしっかりと見据えたうえで、飼育の可否を検討することが求められます。
たとえば、転勤や引っ越しが多い職種の方や、近い将来に結婚・出産・介護などの予定がある方は、家族全体でサポート体制を組めるかどうかを確認する必要があります。
また、パートナーや同居家族が鳥の世話に理解と協力的であるかも大切な判断材料です。
さらに、自分に何かあったときに代わりに世話をしてくれる人がいるか、ペットを引き取ってくれる仕組みがあるかも検討しておくと安心です。
こうした点を踏まえ、感情だけでなく計画性をもって飼育に臨むことが、後悔しないための大きなポイントになります。
動物病院を確保しておく
シロハラインコは見た目が健康そうに見えても、体調不良を隠す傾向が強いため、早期発見のためにも定期的な健康診断が重要です。
特に鳥類は症状が出る頃には病気が進行していることが多く、日常的な健康チェックだけでは見逃してしまうこともあります。
日本国内では鳥類専門の獣医師が少ないため、事前に対応可能な病院を探しておくと安心です。
可能であれば、飼育を始める前に一度その病院を訪れ、診療内容や対応方針を確認しておくとより確実です。
また、定期健診では体重測定、爪やくちばしの状態確認、糞便検査なども実施され、日頃の飼育の質を見直すきっかけにもなります。
いざというときに慌てないよう、アクセスや診療時間、緊急時の対応体制などもあらかじめ把握しておきましょう。
信頼できる販売店・里親制度を利用する
シロハラインコを安心して迎え入れるためには、信頼性の高い販売店やブリーダーを選ぶことが非常に大切です。
健康な個体を扱っているかどうかを見極めるには、施設の清潔さや飼育環境の衛生状態、スタッフの知識や対応の丁寧さなどをチェックポイントとします。
また、可能であれば親鳥の様子や育成環境を見学し、個体の健康状態や性格傾向を確認しましょう。
さらに、ブリーダーや販売店が健康証明書や遺伝的疾患に関する情報を開示してくれるかどうかも重要です。
里親制度を利用する場合も、事前に面談や譲渡条件の確認をしっかり行い、自分の生活スタイルに合った個体かを見極めることがトラブル回避につながります。
迎え入れ後のアフターフォローがあるかも確認しておくと、長期的に安心して飼育を続けられます。
シロハラインコを飼って後悔する理由とデメリット まとめ

シロハラインコの飼育は確かに魅力的で、見た目の美しさやユニークな仕草、知能の高さに惹かれる方も多いでしょう。
しかしその反面、飼育には多くの労力や知識、そして何よりも継続的な責任が伴います。
毎日の世話、放鳥、清掃、健康管理、さらには精神的なケアまで、手間を惜しまずに向き合わなければなりません。
安易な気持ちで迎え入れると、「想像していたより大変だった」と後悔してしまうことも少なくありません。
本記事で紹介したように、シロハラインコには特有のデメリットや注意点が数多く存在します。
そうした点をしっかり理解し、自分のライフスタイルや将来の計画に照らし合わせた上で、長期的な視点から慎重に判断することが、後悔しない飼育の第一歩となります。
関連記事はこちらから!!












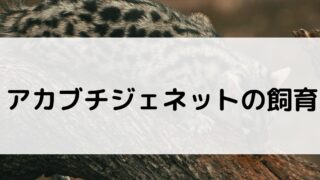




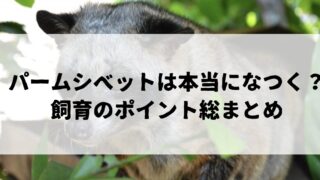




コメント