「アフリカヤマネって、うるさいって本当?」
小さくて愛らしい見た目とは裏腹に、夜行性のアフリカヤマネは思った以上に音を立てることがあります。
特に「夜中にケージから聞こえる音が気になる…」
「静かなペットだと思っていたのに意外と騒がしい」そんな声も少なくありません。
この記事では、アフリカヤマネの行動特性や音の原因、よくある誤解とその対処法、そして飼育前に知っておくべき重要なポイントをまとめました。
かわいいけれど意外とパワフルなアフリカヤマネと、後悔せずに付き合うための情報をぜひチェックしてみてください!
✔ アフリカヤマネは夜行性のため夜間に活動音が目立つ
✔ 鳴き声よりも運動音・ケージ音の方が気になることも
✔ 個体差があり「静かな子」もいる
✔ ケージの設置場所や防音対策で音の軽減が可能
✔ 音に敏感な人は事前に動画などでチェックしておくのがおすすめ
アフリカヤマネはうるさい?

アフリカヤマネの性格
アフリカヤマネは非常に活発で、好奇心旺盛な性格をしています。
小柄な体ながら、驚くほど機敏に動き回ることができ、ジャンプ力や登る力にも優れています。
特に夜になると運動量が増え、ケージ内を縦横無尽に移動し、物をかじったり、ホイールを回したりとさまざまな活動を見せてくれます。
社会性もあり、仲間同士でじゃれ合ったりすることもありますが、警戒心が強い一面もあるため、慣れるまでには時間がかかる場合もあります。
こうした性格から、飼い主としてはその行動を観察するのが楽しい反面、音や動きが気になることもあるかもしれません。
アフリカヤマネはうるさい?


結論から言うと、アフリカヤマネは「うるさい」と感じることがあります。
特に、静かな夜中に活動するため、音に敏感な人にとっては気になる存在になるかもしれません。
鳴き声自体はそこまで大きくはありませんが、甲高く鋭い音を発することがあり、深夜の静けさの中では意外と響きます。
実際には、鳴き声そのものよりも、運動やケージ内での活動音の方が気になるケースも多く、例えばホイールを勢いよく回したり、ケージの金網にぶら下がって飛び跳ねたりと、かなりアクティブな行動を見せることがあります。
また、夜間に物をかじる音や床材を掘る音も加わることで、まあまあのうるささになります。
うるさい、、寝室まで聞こえる😂
先輩はおとなしくお食事🌰#アフリカヤマネ pic.twitter.com/fdRd27BVVa— 多麿 (@mmngamnmn) June 13, 2022
アフリカヤマネはいつうるさい?
アフリカヤマネが最も音を立てるのは、夜間から早朝にかけてです。
夜行性のため、人間が寝ている時間帯に活発になり、物音を立てたり鳴き声を発したりします。
特に午後9時以降から午前3時頃までがピークと言われており、この時間帯はケージ内での運動が最も活発になります。
また、日によっては明け方近くまで元気に動き続けることもあり、飼い主の睡眠を妨げる原因になることも少なくありません。
照明の消灯や生活音の変化など、環境のわずかな変化に反応して一気に活性化する場合もあります。
飼い主の生活リズムと大きくズレるため、初めて飼育する人はそのギャップに驚くこともあるでしょう。
鳴き声と物音
アフリカヤマネは高い声で「チュチュ」や「キキ」といった鳴き声を出すことがあります。
この鳴き声は仲間同士のコミュニケーションや、警戒、欲求を表すものであり、特に複数飼いをしている場合は鳴き声の頻度も上がります。
こちらが実際の鳴き声の動画になります。
また、鳴き声だけでなく、ジャンプしたりケージを走り回ったりする音がかなり響くことがあります。
特に夜間の静かな時間帯には、これらの行動音が増幅されて聞こえるため、より一層うるさく感じられやすいです。
ケージの中でうるさい理由とは?

ケージ内での運動や、ホイール(回し車)の使用、床材を掘る音などが主な原因です。
さらに、給水ボトルのノズルを使う音や、ケージの扉やワイヤー部分にぶら下がって揺らす行動など、思いもよらない部分が音の原因となることもあります。
特に金属製ケージや固い床材を使用している場合、振動や跳ね返りで音が増幅され、反響しやすくなります。
ケージの構造や設置場所、床との接地面なども、音の感じ方に大きく影響するため、飼育環境の見直しも重要なポイントとなります。
発情期やストレスでうるさくなることもある?
発情期や環境の変化によるストレスは、アフリカヤマネがうるさくなる主な要因のひとつです。
発情期には、オスがメスにアピールするために頻繁に鳴いたり、落ち着きなく動き回ったりすることがあります。
メスも不安定な状態になることがあり、通常よりも行動が活発になります。
特に複数飼いをしている場合、同じケージ内でのケンカやテリトリー争い、求愛行動などが原因で大きな物音や鳴き声が発生するケースが少なくありません。
また、ストレスの要因は発情期だけではなく、飼育環境の変化(引っ越しやレイアウト変更)、音や光、気温の変化など多岐にわたります。
飼い主の匂いが変わるだけでも反応することがあり、非常に繊細な一面を持つ動物です。
こうしたストレスによって不安や興奮状態が続くと、落ち着きのない行動や異常な鳴き声が続き、「いつもよりうるさい」と感じられるようになることもあるのです。
ストレスを軽減するためには、静かな環境で安心して過ごせるスペースを確保し、適度な刺激と安定した生活リズムを保つことが大切です。
うるさいアフリカヤマネと静かな子の違い
個体差があり、同じ環境下でも静かな子もいれば、常に活動的でよく鳴く子もいます。
性格は遺伝的要素だけでなく、育った環境や飼育のされ方にも左右されるため、一概に「アフリカヤマネはうるさい」とは言い切れません。
たとえば、幼少期から人に慣れていて安心感を持っている個体は、過剰に鳴いたり暴れたりすることが少ない傾向があります。
また、年齢によっても音の出方は異なります。
若い個体ほどエネルギーがあり、活発に動き回るため、どうしても音が多くなりがちです。
一方、年を重ねた個体は落ち着いた行動をとることが多く、静かに過ごす時間が増える傾向にあります。
健康状態も無視できない要素で、体調が悪いと不安や痛みから鳴く頻度が増すこともあります。
うるささの感じ方には個人差がありますが、性格や状態を観察しながら接することで、その子に合った環境作りがしやすくなります。
アフリカヤマネの鳴き声と他の小動物との比較

ハムスターやフクロモモンガと比較すると、アフリカヤマネの鳴き声はやや高めで鋭い印象を受けます。
ハムスターは比較的静かで鳴くことが少なく、フクロモモンガは「ギューギュー」「キュイキュイ」といった独特の鳴き声を出すことがありますが、アフリカヤマネは「チチチ」「キキキ」といった甲高い鳴き声が特徴です。
これらは主に仲間への呼びかけや警戒時に発するもので、頻度も個体差があります。
サイズが小さいため鳴き声自体はそこまで大音量ではありませんが、鋭さや音質によっては耳に残りやすく、特に夜間は静かな室内で響きやすい傾向があります。
ほかの小動物と比べて、アフリカヤマネは運動量と鳴き声のバランスが取れているものの、静かなペットを求める人には少々騒がしく感じられることもあるかもしれません。
関連記事


アフリカヤマネがうるさいときの対策法

アフリカヤマネがうるさいときの対処法とは?
まずはケージの設置場所を見直すことが大切です。
寝室などの静かな空間は避け、生活音のあるリビングなどに移すと気になりにくくなります。
特に、夜間に活動するアフリカヤマネの音は、静かな部屋ではより目立ちやすいため、多少の環境音がある場所に設置することで相対的に気にならなくなる場合があります。
また、飼い主の生活リズムと動物の行動時間が重なることで、活動音が自然に馴染み、ストレスを感じにくくなることもあります。
加えて、ケージの高さや周囲の物との距離も見直すと良いでしょう。
家具と密着していると音が共鳴しやすくなるため、少し間隔を空けて設置するだけでも響き方が変わることがあります。
環境全体の音のバランスを考えて配置することが、騒音ストレス軽減の第一歩です。
ケージの位置や置き場所が騒音に影響する理由

壁際や床に直置きすると音が反響しやすくなります。
特に硬いフローリングの上では振動音が増幅され、歩行やホイール使用時の音が大きく響きます。
棚の上や振動を吸収する素材の上に設置することで音を軽減できます。
具体的には、防音マットやゴム製のパッドを使って接地面との間に緩衝材を挟むことで、かなりの効果が期待できます。
また、ケージの高さにも注目しましょう。
床に近いほど振動音が伝わりやすくなるため、適度な高さのある台に置くことで防音効果を高めることができます。
加えて、壁に密着させないようにすることで、壁からの反響音も防げます。
音の伝わり方は周囲の材質や家具の配置にも左右されるため、実際に飼育音を確認しながら最適な場所を探ることが大切です。
防音グッズでアフリカヤマネの生活音を軽減する方法
ケージの下に防音マットを敷いたり、カバーで覆ったりすることで生活音を大幅にカットできます。
防音マットは衝撃吸収タイプのものを選ぶと、ジャンプやホイールの振動も和らげてくれます。
また、ケージカバーは音だけでなく光の遮断にも役立つため、ヤマネがより落ち着いて過ごせる環境にもつながります。
さらに、ケージそのものに吸音材を貼り付けたり、周囲に吸音ボードやカーテンを設置することで、部屋全体の音環境を整えることができます。
素材としては、フェルトやウレタンフォームなど、柔らかく音を吸収しやすいものがおすすめです。
最近ではペット用の防音アイテムも多数販売されているため、用途や予算に応じて選ぶとよいでしょう。
夜間の騒音対策におすすめのアイテム
・静音ホイール(ベアリング内蔵タイプで音を最小限に)
・防音マット(ゴム製や厚手のウレタン素材が効果的)
・ケージカバー(遮光性と通気性を兼ね備えたもの)
・吸音パネル(壁やケージの近くに設置すると反響音を防げる)
・緩衝材付き台(家具の上にクッション素材を敷いてケージを置く)
・環境音CDやホワイトノイズマシン(人間側のストレス軽減にも効果あり)
これらのアイテムを組み合わせることで、かなりの静音効果が期待できます。
特に音に敏感な方や、集合住宅で飼育している方にとっては、こうしたグッズの活用が快適なペットライフの鍵となるでしょう。
アフリカヤマネのストレスを減らすと静かになる?
環境を整え、ストレスを減らすことで過剰な鳴き声や暴れ方が落ち着くことがあります。
ストレスを感じる要因としては、騒がしい周囲の環境、頻繁なレイアウトの変更、気温の急激な変化、飼い主との接し方などが挙げられます。
これらのストレス要素を取り除き、アフリカヤマネが安心して過ごせるスペースを提供することが大切です。
例えば、十分な隠れ家を用意することで、不安を感じたときに身を隠せる場所を確保できます。
また、おもちゃや登れる遊具を設置して適度な刺激を与えることも、ストレス軽減に役立ちます。
さらに、毎日の給餌や掃除を決まった時間に行うことで、生活リズムを安定させることができます。
こうした配慮をすることで、アフリカヤマネの行動が落ち着き、結果として鳴き声や物音も少なくなることが多いのです。
どうしても音が気になる人は飼育を見送るべき?
どうしても音に敏感な方は、アフリカヤマネの飼育がストレスになる可能性があります。
特に夜間の物音や鳴き声が気になって睡眠に支障が出るようであれば、飼育は慎重に検討するべきです。
その場合は、事前にペットショップで実際の様子を観察したり、動画サイトなどでアフリカヤマネの鳴き声や行動を確認したりすることをおすすめします。
また、自宅の防音環境や家族との生活スタイルとの相性も重要な判断材料となります。
例えば、夜勤の多い生活スタイルの人であれば夜間の活動音があまり気にならないかもしれませんし、逆に早寝早起きの家庭では支障が大きくなる可能性もあります。
自分の生活に合うかどうかをじっくり見極めたうえで飼育を判断することが、ペットとのよりよい関係を築くうえで不可欠です。
アフリカヤマネがうるさい まとめ

アフリカヤマネはかわいらしい見た目とは裏腹に、夜間にうるさいと感じることがあります。
しかし、適切な対策をすれば騒音はかなり軽減可能です。
ケージの置き場所を工夫したり、防音グッズを使ったり、ストレスを軽減する環境を整えることで、騒音レベルを大きく下げることができます。
また、アフリカヤマネの性格や個体差にも理解を持つことが大切です。
すべてのアフリカヤマネがうるさいわけではなく、静かに過ごす個体もいます。
飼い主の生活スタイルや価値観に合わせて、無理なく共存できる工夫をしていくことで、ペットとの暮らしはより快適なものになります。
夜行性という特性を受け入れつつ、その習性に寄り添った環境づくりを心がけましょう。










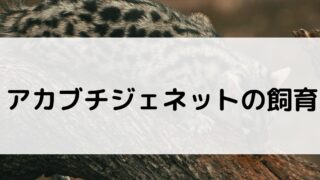




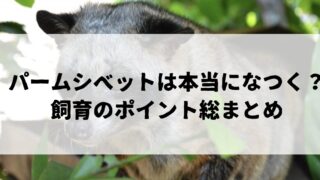






コメント